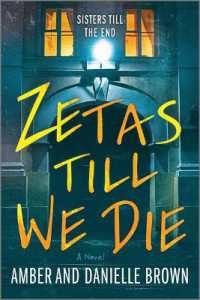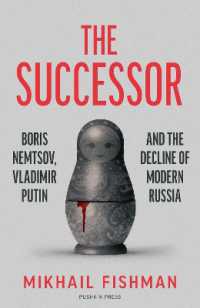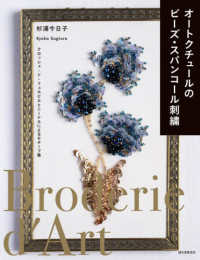出版社内容情報
進化心理学の巨人ダンバーが描く、人類と信仰の20万年。
仏教、キリスト教、ヒンドゥー教、神道……
世界の主要な宗教は、なぜ同じ時期に同じ気候帯で誕生したのか?
カルト宗教はなぜ次々と生まれ、人々を惹きつけるのか?
科学が隆盛を極める現代においても、
宗教は衰えるどころかますます影響力を強めている。
ときに国家間の戦争を引き起こすほど
人々の心に深く根差した信仰心は、なぜ生まれたのか?
そして、いかにして私たちが今日知る世界宗教へと進化したのか?
「ダンバー数」で世界的に知られ、
人類学のノーベル賞「トマス・ハクスリー記念賞」を受賞した著者が、
人類学、心理学、神経科学など多彩な視点から
「宗教とは何か」という根源的な問いに迫った、
かつてないスケールの大著。待望の邦訳刊行。
■ ■ ■
集団内に協力行動を生みだす信仰心も、
集団の外に対しては反社会的行動の原動力となる。
宗教的アイデンティティが国家に利用されるとき、悲劇は起こる。
――フィナンシャル・タイムズ紙
宗教と人間の生活のあり方は、かくも複雑なのである。
本書は、その両方を進化的ないきさつから説明しようと、
真に大きな考察を展開しようと試みる大作である。
――長谷川眞理子(進化生物学者、総合研究大学院大学名誉教授/「解説」より)
■ ■ ■
内容説明
科学が隆盛を極める現代においても、宗教は衰えるどころかますます影響力を強めている。ときに国家間の戦争を引き起こすほど人々の心に深く根差した信仰心は、なぜ生まれたのか?そして、いかにして私たちが知る世界宗教へと進化したのか?「ダンバー数」で世界的に評価され、「人類学のノーベル賞」と称されるトマス・ハクスリー記念賞を受賞した著者が、人類学、心理学、神経科学など多彩な視点から「宗教とは何か」という根源的な問いに迫った、かつてないスケールの大著。
目次
第1章 宗教をどう研究するか
第2章 神秘志向
第3章 信じる者はなぜ救われるのか?
第4章 共同体と信者集団
第5章 社会的な脳と宗教的な心
第6章 儀式と同調
第7章 先史時代の宗教
第8章 新石器時代に起きた危機
第9章 カルト、セクト、カリスマ
第10章 対立と分裂
著者等紹介
ダンバー,ロビン[ダンバー,ロビン] [Dunbar,Robin]
オックスフォード大学進化心理学名誉教授。人類学者、進化心理学者。霊長類行動の世界的権威。イギリス霊長類学会会長、オックスフォード大学認知・進化人類学研究所所長を歴任後、現在、英国学士院、王立人類学協会特別会員。世界最高峰の科学者だけが選ばれるフィンランド科学・文学アカデミー外国人会員でもある。1994年にオスマン・ヒル勲章を受賞、2015年には人類学における最高の栄誉で「人類学のノーベル賞」と称されるトマス・ハクスリー記念賞を受賞。人間にとって安定的な集団サイズの上限である「ダンバー数」を導き出したことで世界的に評価される
小田哲[オダサトシ]
翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かんやん
原玉幸子
特盛
vy na
エジー@中小企業診断士
-

- 電子書籍
- 不知霧~そこから生きては出られない~【…