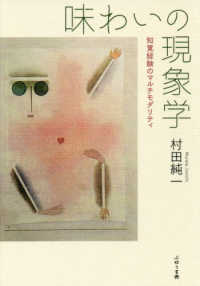内容説明
自然は天才だ!世界初の成長する植物ロボット“プラントイド”を開発した科学者が明かす、“生物学×テクノロジー”の驚きのコラボレーション。自然界に学ぶ、人間の想像を超えたものづくりとは?
目次
すべてが始まった場所
新たな時代のロボット工学
インスピレーションを探し求める科学者たち
自然の実験室
進化の謎に挑む動物ロボット
私たちに似た機械
植物は隣にいるエイリアン
ロボット学者、偏見の壁にぶつかる
見えない運動
プラントイド ある革命の歴史
植物の知能
水の力
よじのぼる植物ロボットを目指して
著者等紹介
マッツォライ,バルバラ[マッツォライ,バルバラ] [Mazzolai,Barbara]
マイクロシステム工学の博士号をもつ生物学者。イタリア技術研究所(IIT)のマイクロバイオロボティクスセンターのディレクター。2015年、ロボット研究者が集う最大の国際科学コミュニティ“Robohub”で「ロボット業界で知っておくべき25人の女性」の一人に選出されたほか、数々の賞を受賞。植物の根に着想を得た世界初のロボット“プラントイド”を開発。現在、GrowBotプロジェクトを立ち上げ、つる植物を持続可能なインテリジェントテクノロジーに変換しようと取り組んでいる
久保耕司[クボコウジ]
翻訳家。1967年生まれ。北海道大学卒業。訳書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
内島菫
16
ロボット工学版ミメーシス的トートロジー。つまり、技術と自然の間で人を媒介にして行われる発見と創造(もしくは創発)のキャッチボールによる好循環。この循環は植物の回旋運動と相似を為しているようでもある。12億年前には藻類が、5億年前には陸上植物がすでに存在していたのに対し、ヒト属が現れたのは200万年前だから、我々の方が植物から見ればエイリアンだ。それほど長い間をかけて自然は実験をしてきたのだから、植物が動物とは全く種類の異なる驚異であるのはむしろ当たり前と言えるだろう。2023/03/01
PenguinTrainer
8
生物を模倣したバイオミメティックの概要と、筆者らが取り組んでいる植物模倣のロボットについて書かれた本。 前半の動物をモデル化のソフトロボティクスの歴史もきれいにまとまっているし、筆者らが今取り組んでいる植物の根を再現したロボットというのも非常に面白かった。2022/03/31
スダタロー
3
今当たり前に使われている技術のなかには自然から着想を得たものが多いそう。「あんなものやこんなものまで?!」という新鮮な驚きがあり知的好奇心が刺激される。なにより著者が自然を愛して技術の未来を信じていることに勇気づけられる。2021/07/12
人生ゴルディアス
2
光合成を人工的に再現しようとする研究はあるけど、そう言えば植物を模倣するロボットってなかったな……と思うなど。とはいえ本書は一般向け科学書の中でもさらにライトな部類なので、なんだかいまいちすごさがわかりにくかった。生物模倣のロボットについては『生物模倣』と言うそのままのタイトルの本があったり『サイボーグ化する動物たち』などは動物→機械化の方向性だが、潮流なのかな。本書は内容がライトなんだから、勉強用の参考書籍をもっとがんがん乗せて欲しかったかな。2021/09/18
mitsu
1
AI関連の書籍で興味があり読みました。最近までのロボティクスの話から植物を生態から着想した植物ロボット〈プラントイド〉までのことを開発者の著書による内容でした。ロボットと言うと素早く効率的に作業するイメージですが、これからはエネルギー効率の良いロボットという観点からの内容は新鮮でした。従来のロボットの概念を変えられる内容で物事を考える上での着眼点に関しても興味深かったです。2022/03/04
-

- 電子書籍
- 無職が最強であることを俺だけが知ってい…
-
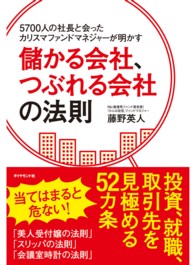
- 電子書籍
- 儲かる会社、つぶれる会社の法則 - 5…