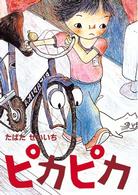出版社内容情報
ヘーゲルの『精神現象学』は徹頭徹尾時代の産物であり、先行者と同時代の人々との論争なくしては成立しなかった。カントの『純粋理性批判』の登場という衝撃によって生まれた様々な哲学論議、とりわけその中で醸成されたスピノザ主義を軸に検討し、時代のコンテクストをも踏まえながら、ヘーゲル哲学を「学」の構想のもとに位置づける。
内容説明
ドイツ古典哲学の新たな水脈、ヘーゲルはいかにして「哲学者」になったか。
目次
第1部 ドイツ古典哲学の問題圏―スピノザとカント(一八世紀ドイツにおけるスピノザをめぐる論争;カント哲学の遺産―カントvs.ヤコービ、マイモン)
第2部 哲学の「根本原理」とその理論的進展―「理性」と「感情」(テュービンゲン・シュティフトにおけるフラットの「形而上学」;フィヒテの「知識学」の受容;フィヒテvs.「批判的懐疑主義」;フィヒテ‐シェリングの知的交流―「知的直観」をめぐって;「私たちの精神の連盟の時代」―フランクフルト‐ホンブルク・コンステラツィオンのキーコンセプトとしての「生」)
第3部 「学」の体系としての「精神現象学」(「学」の必然性とは何か―「カオス」から「秩序」へ(1)
「宗教」章冒頭部の課題とその統体化機能―「カオス」から「秩序」へ(2)
「絶体知」は成立したのか―ヘーゲル青年期一九年の総決算)
総括 ヘーゲルはいかにして「哲学者」になったのか
著者等紹介
久冨峻介[クドミシュンスケ]
1990年福岡県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。現在、京都大学人文学連携研究者。哲学・思想史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme