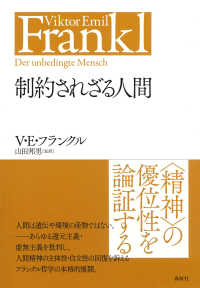内容説明
製薬企業が53件の研究を追試したところ、結果を再現できたのはそのうちわずか6件。再現失敗率、約90%―命を救うはずの研究が、低すぎる再現性のために、無用な臨床試験、誤った情報、虚しい希望を生みだし続ける。ずさんな研究はなぜ横行するのか?その影響はどこまで及ぶのか?改革は可能か?トップ研究者から、政府組織の要人、業界の権威や慣習に立ちむかう「反逆児」、臨床試験に望みを託す患者まで、広範な調査・取材を基に、ひそかに生命科学をむしばんできた「再現性問題」の全貌をあぶりだす。
目次
第1章 製薬業界を揺るがした爆弾発言
第2章 無数の落とし穴
第3章 バケツ一杯の冷や水
第4章 惑わすマウス
第5章 疑惑の細胞と抗体
第6章 結論に飛びつく
第7章 自分の研究をさらせ
第8章 壊れた文化
第9章 精密医療のハードル
第10章 規律をつくり出す
著者等紹介
ハリス,リチャード[ハリス,リチャード] [Harris,Richard]
科学ジャーナリスト。科学・医療・環境を専門とし、ナショナル・パブリック・ラジオの記者として三〇年以上の実績がある。AAAS(アメリカ科学振興協会)の科学ジャーナリズム賞を三回受賞している。ワシントンDC在住
寺町朋子[テラマチトモコ]
翻訳家。京都大学薬学部卒業。企業で医薬品の研究開発に携わり、科学書出版社勤務を経て現在にいたる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
羽
11
☆☆☆ とある製薬企業が新薬開発につながる論文を探し、再現しようとした。ところが、論文執筆者たちの協力を得ても、再現できた実験はたったの一割しかなかった。二〇一二年、この「再現性」の問題は『ネイチャー』誌に掲載され、一躍注目を浴びた。本著で紹介されるのは、ノーベル賞受賞者や研究の研究をする研究者たち。実験の場所や材料の数や器具の洗剤によっても結果は左右されるし、そもそも世界共通の実験ルールがないのだから、再現し難いし、科学者のバイアスもあれば熾烈な出世レースもあるのだ。2019/08/16
DEE
8
医学がめざましい進歩を遂げているのに完治できる病気が増えないのはなぜか。新たな発見が毎日のようにあるのに、その後についてはあまり耳にしないのはなぜか。 そもそも実験材料が誤っていたらその後の研究は全くの無意味となるのだが、そういう事が日常茶飯事だという。 論文を書かなければ今のポストが危うくなるという立場では、質より量となってしまうのは仕方ないことかもしれない。でも無意味な事に莫大なお金と時間をかけ、その結果治療が遅れ救えたかもしれない命が消えていく。 やはりそれは医学としては根本的に間違っている。2019/06/07
HK
3
新薬開発のターゲットになる生命科学研究の約90%が再現できない(「再現性の危機」)という衝撃的な調査結果からはじまる本書は、そうした〈クライシス〉の原因となっている①現在の生物学研究モデル・ツール・手法に不可避な不安定さ、②統計処理に関する研究者の知識不足とバイアス、③生命科学分野の過剰な競争ゆえの誤りや不正および閉鎖性といった不適当な文化、について解説する科学ノンフィクション。深刻な状況を丁寧に論証するのとともに、希望になるかもしれない科学界の動きも紹介する良書。2019/12/28
takao
2
ふむ2022/12/08
Wyoshi
1
生命科学研究の関係者は必読 何故生命科学の論文の多くは再試ができないのか? 研究者の野心や身分保身のための捏造、研究者自身の未熟・無知による不適切な実験法と解析、そして生命自体の持つ複雑性が主な原因であるとする。 実際自分も自身で行った実験が試薬のロット替えによりどうしても再現しなかった経験がある。 対処法はいまだに模索中というのが現状だ。 STAP細胞事件も、研究者の資格は問われたが細胞の存在自体が否定されているわけではない。 それは単に再現ができなかっただけなのかもしれない。2024/02/09