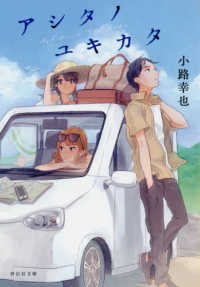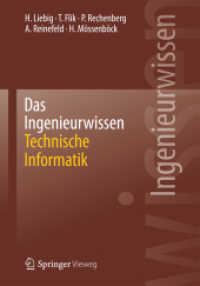内容説明
バイオテクノロジーは動物をどのように作り変えたのか?リモコン操作できるラット、緑色に発光するネコ、製薬工場と化したヤギ…現代科学が生み出す改造動物の最前線。
目次
第1章 水槽を彩るグローフィッシュ
第2章 命を救うヤギミルク
第3章 ペットのクローン作ります
第4章 絶滅の危機はコピーで乗り切る
第5章 情報収集は動物にまかせた
第6章 イルカを救った人工尾ビレ
第7章 ロボット革命
第8章 人と動物の未来
著者等紹介
アンテス,エミリー[アンテス,エミリー] [Anthes,Emily]
科学ジャーナリスト。「ニューヨークタイムズ」「ネイチャー」「サイエンティフィック・アメリカン」「ワイアード」「ボストン・グローブ」などの各紙誌に執筆。マサチューセッツ工科大学からサイエンス・ライティングの修士号、イェール大学から科学史・医学史の学士号を取得。ニューヨークのブルックリン在住。『サイボーグ化する動物たち』で、優れた科学書に贈られる「AAAS(アメリカ科学振興協会)/Subaruサイエンスブックス&フィルム賞」を受賞している
西田美緒子[ニシダミオコ]
翻訳家。津田塾大学英文科卒業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
starbro
98
文春の書評欄で見てタイトルに興味を持って読みました。理論的にはかなり進んでいるバイオテクノロジーですが、実践面ではまだ上手くいっていない様です。神の領域なのかマッドサイエンティストなのか解りませんが、かなり危うい状況にある気がします。将来とんでもない突然変異が生じたり、モンスターが誕生するかも知れません。先日読んだ葉真中顕の「ブラック・ドッグ」に通ずるものがあります。タイトルは原題の「フランケンシュタインの猫」の方が、本書の内容を如実に伝えていると思います。10月は本作で読了です。2016/10/31
taku
21
バイオテクノロジーは、いまここまで出来て、まだここまでしか出来ない。ペットのクローンを私も望むかもしれない。動物や虫を思うように操れたら楽しそうだ。技術の進歩に興奮を覚える反面、疑念も膨らむ。本当に他生物の暮らしも向上するか?絶滅を防ぐなら種のコピーより、まず人口爆発への対策をだな。画期的な、魔法のようなBTが救ってくれるか?技術は信用できても人はどうなの?未来への期待と不安も想像させてくれる、最近読んだ科学本では一番刺激があった。2018/06/08
GASHOW
12
サイボーグは、機械部品をイメージする。DNAの改造は、倫理的な問題にも発展する。ブタの臓器を移植することでブタ人間とはいわないが、マウスに人の脳を作り出すことなど嫌悪を感じる。欧米では、DNA操作について規制があるが、人類はタブーをおかしてゆくのかもしれない。動物を実験としては既にはじまっている。2016/09/09
HMax
9
「嫌悪因子」これがキーワード。自分の子供を救うためであればクローニングでもサイボーグでも藁にも縋る思いでしょう。今では一般的な不妊治療でさえ、つい何十年か前まで試験管ベイビーと呼ばれていたことを思い出します。何十年後かには、人間のサイボーグ化が当たり前になって、パラリンピックやオリンピックが無意味な世の中になって欲しいと思います。そうなればホーム柵がなくても線路に落ちて亡くなることもないでしょうし。 それにしてもクローン牛が種牛として普通に売買されていると聞いて驚きました。 2016/10/15
Kentaro
8
ダイジェスト版からの感想 電子工学とコンピューター技術の進歩に伴って動物のからだを機械と一体化が可能になり、ごく小さい電極でラットの脳をハイジャックし、まるでリモコン玩具のように複雑な障害物コースを誘導することもできる。材料科学と獣医外科のめざましい発展は傷ついた動物のために人工の手足を作るのに役立っているし、頭のなかで考えるだけでロボットアームをコントロールできるようにサルを訓練することもできる。倫理学者と活動家は、人間がほかの種に、当事者の同意などとうてい得られない状況で手を加えてよいのかと憂慮する。2018/04/01
-
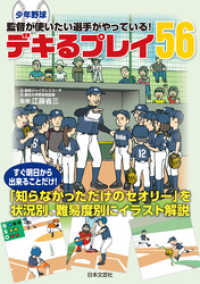
- 電子書籍
- 少年野球 監督が使いたい選手がやってい…
-
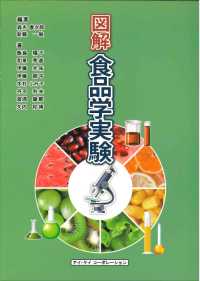
- 和書
- 図解食品学実験