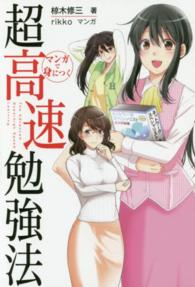出版社内容情報
氷嚢、ブラシ、ティーカップ、砂糖の精製、手術糸、ベニヤ板の接着、醤油、菜種の栽培、かんざし、綿打ち、石油関連火災の消火……と、牛の関係は?
資源としての動物に向けられた熱いまなざし・ひらめき・工夫が、わたしたちにもたらしたものをたどりながら、人間と動物の生命の価値・境界をさぐる!
近代以前の日本では、家畜の利用は食用を目的とするものではなく、牛馬が死ぬと皮・骨・筋・脂などが取引された。近代以降、食肉産業が本格的に展開されるようになると、家畜への関心は高まったが、その中心は「肉」と「皮」であった。近年のBSE発生という不幸なできごとが問いかけているのは、単に「牛肉問題」ではない。人間が生命あるものを利用するために考えなければならないことは何か、これまで培ってきた動物体利用の技術と思想を共通の財産に、今後の進む道を見極めたい。
はじめに
第1章 骨の利用について
1 骨細工
2 骨粉
3 骨灰・骨炭
・骨灰
・骨炭
4 骨油・膠
第2章 血液の利用について
1 血はどのように認識されたか
2 血はどのように使われたか
・近世における血の利用への関心
・近代の屠場と獣血の利用
・屠場廃水処理問題と獣血利用の新展開
3 獣血はなぜ活用されなかったか
第3章 筋の利用について
第4章 臓器などの利用について
1 工業用
・膀胱
・腸
2 脳漿なめし
3 移植用臓器
4 薬用
・胆嚢
○近世期の熊胆利用
○様々な動物胆利用
○熊胆の処理方法と種類
・体内結石
1 牛黄
○古くから利用されてきた牛黄
○牛黄と仏教
○注目されてきた牛黄
○近世における牛黄の利用
2 馬糞石
3 オクリカンクリ
4 龍涎香
5 真珠
・近代以降の臓器由来物質利用
1 酵素
○ペプシン
○パンクレアチン
○レンネット(キモシン)
2 ビタミン
○肝油
3 ホルモン
○アド棄物」の資源化を目指した化製業
おわりに
『歴史民俗学』誌に不定期掲載されていた「モノになる動物のからだ」が大幅加筆の上、ついに単行本化されました。
●装丁=臼井新太郎
内容説明
近代以前の日本では、家畜の利用は食用を目的とするものではなく、牛馬が死ぬと皮・骨・筋・脂などが取引された。近代以降、食肉産業が本格的に展開されるようになると、家畜への関心は高まったが、その中心は「肉」と「皮」であった。近年のBSE発生という不幸なできごとが問いかけているのは、単に「牛肉問題」ではない。人間が生命あるものを利用するために考えなければならないことは何か、これまで培ってきた動物体利用の技術と思想を共通の財産に、今後の進む道を見極めたい。
目次
第1章 骨の利用について(骨細工;骨粉 ほか)
第2章 血液の利用について(血はどのように認識されたか;血はどのように使われたか ほか)
第3章 筋の利用について
第4章 臓器などの利用について(工業用;脳漿なめし ほか)
第5章 化製業試論―2001年9月、そして(近世の家畜利用と死牛馬処理;食用家畜飼養の本格化と家畜体の利用 ほか)
著者等紹介
中島久恵[ナカジマヒサエ]
1957年生まれ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- ヒメネス詩集 世界の詩