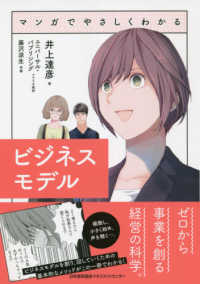内容説明
演劇論というものは、実際の個別的な演劇芸術と無関係には存在し得ない。しかし演劇論は、時間・時代と空間・地域の関わり方において、個々の演劇の存在から自立してもいる。もともと普遍性のある演劇論は、たとえ特定の古い演劇を対象とする場合でも、時代を横断するパースペクティヴを持ってアプローチしている。しかも演劇論が生みだされる時代に深く根ざした視点が前提にある。空間においても同様のことが言える。時代と世界を横断するパースペクティヴと、いま、われわれのいる日本の視座。両者の交わる一点において、本書の論文は、同じ一つの時代=場のいわば心性とも呼ぶべきものを共有し、全体でダイナミックなうねりを成している。
目次
1 新しい上演パラダイムに向けて(上演はいかに想起されるか;演劇におけるアイロニーについて;シェイクスピアはどこにいるのか―現代上演における「作者」シェイクスピアの在処について ほか)
2 近代における古典(人形から人間へ―中国泉州・道士の芝居「打城戯」の選択;「観客の代表」としてのワキについて(再考)―明治以降の「劇」フレームと中世の能
坪内逍遙の「比較演劇」―「遊び」と「研究」の間)
3 変革者としての作家たち(「ここで座り、考え込む」―ニコラス・ユーダルと〔瞑想的モノローグ〕の成立について;家族、社会、個人のモダニティ―ユージン・オニール『喪服の似合うエレクトラ』における家族の表象;ベケットと身体―『ゴドーを待ちながら』における道化的身体をめぐって ほか)