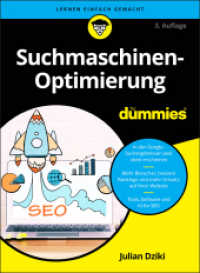内容説明
女性作家の物語には優れた作品、興味深い作品が多い。これまで分析対象とされてこなかった、女性作家の児童文学・教科書教材を中心とした物語の読解を行う。また、女性というカテゴリーに注目し、男らしさ・女らしさ、典型をめぐる争闘、通過儀礼や行動様式を論じる。
目次
1 安房直子(創作の方法;時間と共同体―小学校童話教材;スペクタクルと覚醒―中学校教材;無気力なファンタジー)
2 あまんきみこ(不可視を可視化すること―あまんきみこの世界;日常空間のファンタジー性、あるいは空間の変質―『鳥よめ』『空の絵本』;比喩と虚構―「わたしのかさはそらのいろ」「おかあさんの目」;物語の効能と主体形成―「いっかい話、いっかいだけ」「青い柿の実」「夕日のしずく」;外部空間化された意識・記憶―『だあれもいない?』;夢・白昼夢の物語―「口笛を吹く子」;連作による幻想長編の構成―『北風をみた子』;メタフィクションの挑戦―『もうひとつの空』)
3 儀礼・儀式とステージ(透明と障害―香魚子;輝くことの物語と過剰―劇場版『花咲くいろはHOME SWEET HOME』;終わらないことの夢想―吉本ばなな;らしさを生きる/らしさに抗う―山内マリコ)
4 小川洋子(虚構の民俗的カテゴリー―「百科事典少女」;グロテスクのゆくえ―「愛されすぎた白鳥」「果汁」;媒介者の機能―「缶入りドロップ」「トランジット」「博士の愛した数式」「巨人の接待」「ハキリアリ」;プロットの修辞学―『アンジェリーナ』;パサージュと窪み―『最果てアーケード』)
著者等紹介
西田谷洋[ニシタヤヒロシ]
1966年生まれ。金沢大学大学院社会環境科学研究科修了。博士(文学)。富山大学人間発達科学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- トラウマから回復するセラピーヨガ - …
-
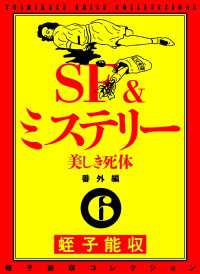
- 電子書籍
- 蛭子能収コレクション 番外編 6 SF…