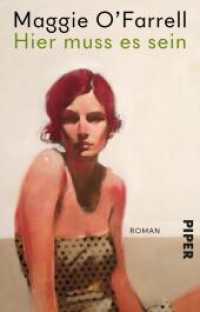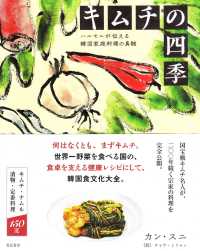出版社内容情報
離れて暮らしていると、介護や病気、不慮の事故……親のことが心配になりますね。そんな時、開いていただきたいのがこの本。遠距離介護の取材を長年つづけ、NPO団体の理事長となった著者が贈る介護応援ブックです。知って役立つ介護サービス、制度、お金、生活の知恵が満載です。
第1章 離れた親の暮らしをささえる
【別居? 同居?】
親のこと、気にはなるのですが、なかなか実家へ行けません。
●親の「普段どおり」を知っておくためにも、元気な頃からの交流が大切です。
いずれは「呼び寄せる」ことが、親の幸せになるのでしょうか?
●離れて暮らすメリットもいっぱいあります。話し合ってみましょう。
親とは長電話になるのがおっくうで、なかなか電話をかけられません。
●おっくうなら、きょうだいや孫世代も巻き込んでみましょう。
認知症と診断されました。担当医は「ひとり暮らしは無理」といいますが。
●なにができて、なにができないかをしっかり観察することが重要です。
【日常生活】
過疎地のため生活が不便です。便利な交通手段はありませんか?
●地域に有料送迎などの非営利活動サービスがないか確認してみましょう。
ゴミ出しをお隣の人に頼めますか。お礼はどうすればいいでしょうか。
●思いきってご近所の人にお願いしてみるのがいいでしょう。
しっかり食事をとっていないようです。薬も飲んでいないのですが。
●共食の機会を増やす方法を考えてみるのも、ひとつの方法です。
親の郵便管理が難しくなってきました。なにか方法はありませんか?
●帰省したときに、確認漏れがないかチェックするのが一番だと思います。
親の家は整理整頓ができておらず、大切な書類があちこちに置かれています。
●大切な書類は整理して、収納場所を一緒に考えましょう。
【安否・緊急連絡】
病気になって苦しくなったときに、通報できるようにしておきたい。
●緊急通報システムを導入すると、安心感が高まります。
携帯電話に親の様子を知らせてくるサービスってどんなものですか?
●普段どおりの生活を送っていることを確認するサービスから始めてみては。
お隣の人にいざというとき親の様子をのぞいて、と頼むのは迷惑でしょうか。
●自分の代わりにかけつけてくれる人を確保しておくとよいでしょう。
【病気の心配】
母親はすっかりふさぎこんでいます。「うつ病」ではないかと心配です。
●高齢者のうつ病の症状はさまざま。早めに専門医を受診しましょう。
ジェネリック医薬品は価格が安いのですが、どうすれば使えますか?
●担当の医師や薬剤師に、利用について相談してみるといいです。
親が認知症かもしれません。病院の何科へ連れていけばいいですか?
●親のプライドを傷つけないように、精神科などを受診することが大切です。
親とずっと不仲です。認知症らしいのですが介護する自信がありません。
●福祉サービスや施設入居を選択肢に考え、無理はしないことがポイントです。
親が入院しました。完全看護なのに、付き添うようにいわれたのですが。
●基本的に家族が付き添う必要はないのですが……。
入院してすぐに転院のことを考えておく方がいいのはなぜですか?
●3ヶ月以内での転院が一般的ですから、心の備えをしておきましょう。
60歳の父が末期がんで入院しています。在宅で看取りたいのですが……。
●40歳以上の末期がんの在宅療養には、介護保険が心強いサポートとなるでしょう。
第2章 介護サービスを使う
【サービスの内容】
高齢者向けのサービスには、どんなものがあるのでしょうか。
●種類は介護保険、自治体、ボランティア、民間などがあります。
親の暮らす自治体にどのようなサービスがあるか知りたいのですが。
●高齢者向けのサービスをまとめた冊子やパンフレットの郵送を依頼できます。
申請のときは帰省するべきですか? 認定調査はどうすればいいですか?
●申請時よりも、認定調査のときに付き添った方がいいでしょう。
介護認定調査ではどのようなことを聞かれますか? その後の段取りは?
●心身の状態について聞かれます。結果は申請から30日以内に連絡が来ます。
介護保険の介護予防サービスとは、どのようなものですか?
●介護予防給付は、介護保険サービスの一環です。
要介護になることを予防したいのですが、元気な親だとサービスを使えませんか?
●自立でも、リスクが高いと認められればいまから利用できます。
介護度によって利用できるサービス額はどれくらい違うのですか?
●支給限度額は要介護1で約16・5万円、 要介護5で約35・8万円です。
介護保険で介護ベッドや車いすをレンタルで借りられますか?
●「要介護2」以上の介護度であればベッドや車いすをレンタルできます。
医師から介護保険の利用をすすめてきません。申請は時期尚早ですか?
●医師から介護保険の申請をすすめてくるとは限りません。
いいケアマネジャーは、どうやって見つければいいのですか?
●近所の評判を参考に、話をしっかり聞いてくれる事業者を選びましょう。
ケアマネジャーを頼りにしているのに、電話をかけても留守ばかりで困ります。
●コミュニケーションには、ファクスやメールを活用するのも方法です。
事業者のケアプランがぴんとこないので、子が立てることはできますか?
●自分や家族がケアプランを立てる「自己作成」も選択可能です。
【在宅で介護】
親のクチグセは「ひとりでなんでもできる!」なので困ります。
●無理強いせず、ゆっくり説得しましょう。適切なタイミングが見つかります。
母親が急逝。残された父親は家事ができず困っています。
●有償ボランティアの家事援助サービスなどを検討してみるといいでしょう。
介護の専門家が実家を定期的に訪問してくれたら安心です。
●毎日、父親が誰かと顔を合わせるようスケジュールを組むと安心です。
お風呂の事故が心配です。手すりや段差撤去は介護保険でできますか?
●介護保険では20万円を上限に住宅改修工事ができます。
認知症の場合に使えるサービスは、どのようなものがありますか?
●住み慣れた地域で安心して暮らせる「地域密着型サービス」があります。
介護サービスを行うボランティア団体があると聞きましたが……。
●ほとんどは有償ボランティア。問い合わせは地域の社会福祉協議会へ。
食事の宅配サービスをする会社が故郷にあるか知りたいのですが。
●地域包括支援センターや近所の人から情報収集をしましょう。
いろいろなサービスを使っても、在宅での限界があると思います。
●無理ということはありませんが、在宅での暮らしは難しくなるケースも。
親を呼び寄せても介護保険のサービスは受けられますか?
● 引き続き同じように利用することができます。
入院したら介護保険のサービスを利用できないって本当ですか?
●確かに、入院中は介護保険のサービスを受けることはできませんが……。
【施設の利用】
「老いても自立して暮らすよ」と両親は元気です。どんな住まいが安心ですか?
●老いても安心して暮らせる老後の住まいや施設はいろいろあります。
介護保険で入れる施設には、どのようなものがありますか?
●特別養護老人ホームなどに早めに申し込みをするといいでしょう。
家庭的な雰囲気の小グループ化した施設が増えていると聞きますが。
●ユニットケアのグループホーム、新型特別養護老人ホームもあります。
病院から在宅に戻す前にしっかりリハビリを受けさせたいのですが。
●病院から在宅への橋渡しをする病院や施設を検討しよう。
親が大部屋はいやだから有料老人ホームに入るというのですが。
●経済的なことはもちろん、相性、立地などもよく検討して選びましょう。
寝たきりの父と元気な母が一緒に入れる介護施設はありますか?
●介護付有料老人ホームなら一緒に入居できるところもあります。
介護施設に入居するのですが、実家を売るべきでしょうか?
●親の性格などをよく考えて、最良の選択をしましょう。
地域にケアハウスができますが、終の住まいになるのでしょうか?
●「特定施設」に指定されていれば介護体制が充実している。
有料老人ホームに入居したのですが、倒産しないか不安です。
●情報開示がどの程度なされているかなどをチェックしましょう。
第3章 知っておきたいお金と制度
【交通費】
頻繁に通う私のために母が交通費をくれるのですが、もらってもいいのでしょうか?
●交通費を差し出されたら「ありがとう」と受け取るといいでしょう。
帰省手段は鉄道や飛行機です。安いチケットを買う方法はありませんか?
●交通機関各社のホームページは要チェックです。
帰省に高速バスを使いたいのですが、料金が安いぶん、疲れませんか?
●体調やスケジュールに合わせた利用がおすすめです。
介護のための帰省にかかる交通費の割引サービスはあるのでしょうか?
●「介護帰省割引」を実施する航空会社もあります。
【医療・保険費】
高齢者の医療費はどういうしくみですか? 窓口負担は下がるのでしょうか?
●老人保健制度で受診するのは75歳の誕生日の翌月から。今後負担はアップ。
高額療養費制度の対象になるのはどういう場合ですか?
●原則、月4万4400円(70歳以上・2006年10月以降)以上払った場合に戻されます。
介護保険の利用者負担ですが、1割でもけっこうな額になります。
●一定額を上回ると「高額介護サービス費」として支給されます。
親の使った医療費や介護費について税金の控除ができますか?
● 親を「扶養控除」としているなら、医療費控除もでき、介護費用も合算できます。
実家の親を「扶養控除」にするのと、「世帯分離」とどっちが得ですか?
●「世帯分離」が広がっているのは事実です。
介護保険と身体障害者手帳とを両方申請することができますか?
●障害が認められれば、医療費補助や税の減免が受けられる場合もあります。
【保険・金融商品】
民間介護保険に入ると遠距離介護にどれくらい役に立ちますか?
●商品ごと給付の条件、内容が異なるので、納得してから加入しましょう。
銀行や郵便局の介護貯金・介護支援定期預金って役に立つのですか?
●金利上乗せのほか、諸サービスが付加される商品もあります。
実家を担保に毎月の生活資金を借りられる制度ってどんなものですか?
●「リバースモーゲージ」というサービスです。国の制度としても実施してます。
【財産管理】
離れて暮らす母親に毎月お金を渡したいのですが、手数料がかかりすぎます。
●口座を工夫することで、振込み手数料が無料になることもあります。
内容説明
地図上の距離は遠くても、心の距離は近くありたい。本書は、ほんとうに必要なときにささえあって、親と子それぞれが自立して暮らすための本です。
目次
第1章 離れた親の暮らしをささえる(別居?同居?;日常生活 ほか)
第2章 介護サービスを使う(サービスの内容;在宅で介護 ほか)
第3章 知っておきたいお金と制度(交通費;医療・保険費 ほか)
第4章 よりよい介護を行うために(夫婦の連携;きょうだい関係 ほか)
巻末資料
著者等紹介
太田差惠子[オオタサエコ]
1960年生まれ。介護・暮らしジャーナリスト。AFP(日本FP協会)高齢化社会においての「暮らし」と「高齢者支援」の2つの視点からの新しい切り口で執筆、講演活動等を行う。1996年、親世代と離れて暮らす子世代の情報交換の場として「離れて暮らす親のケアを考える会パオッコ」を立ち上げ、2005年法人化。現理事長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 電子書籍
- オルフェウスの窓 外伝~コラージュ