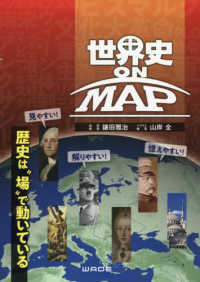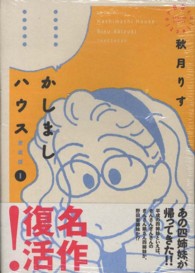内容説明
ノーベル賞受賞のワトソン博士が赤裸々に語る自叙伝的エッセイ。二重らせん発見から50余年。研究者のあり方や研究の進め方について、率直な教訓をあげる。
目次
子ども時代に身に付けた習慣
学部学生だったころに身に付けた習慣
大学院で身に付けた習慣
ファージグループが採用していた習慣
野心に燃える若き科学者として教わった習慣
価値ある科学を行うに必要な習慣
終身在職権のない教授として取っていた習慣
活気ある研究を促すために採用した習慣
重要ではない大統領顧問になって知った習慣
ノーベル賞受賞者にふさわしい習慣〔ほか〕
著者等紹介
ワトソン,ジェームス・D.[ワトソン,ジェームスD.][Watson,James D.]
DNA二重らせん構造の発見で、1962年ノーベル生理学・医学賞を受賞。1968年から1993年までコールドスプリングハーバー研究所所長、その後2007年まで会長
吉田三知世[ヨシダミチヨ]
京都市生まれ。京都大学理学部物理系卒業。英日・日英の翻訳業に従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
R
14
DNAの二重らせん構造を解き明かしたワトソン博士の自伝でした。半生をいくつかのポイントにわけて、その都度に習慣として、反省として得たことをまとめながら事実を網羅しています。周辺事実や関係を知っていると至極愉快なのであろうと思うものの、山ほど出てくる関係者に混乱して読むのに難儀しました。女好きであること、向上心が人並みはずれていること、いかにも天才で高慢というのを隠そうともしないことなど、ある種人間味に溢れた姿が見えてくる本でした。2017/01/19
incognito
2
ワトソン先生がかなり女好きだったということが伺える本。教訓が章末についているが、これは「教科書には章ごとにキャッチーな見出しをつけたほうがよい」という彼の信念に依るものだと思うのであんまし間に受けずに。参考になったのは米国における科学研究のあり方と彼が理想とする教育のあり方。研究と教育がうまくかみあっていて学生が知的好奇心を常に刺激される様は羨ましかったし、研究が人との関わりでどのように進んでいくのかをつまびらかに知ることができた。難点は訳者の読点の打ち方(と恐らく元の文章)がヘタクソで読みにくい事。2011/01/04
fathermacker
1
「じつのところ、最終学年はすべての講座でAの評価であったのである」とか書かれてもまったく嫌みにならないワトソン先生の自伝。科学者の姿勢が学べる。おべんきょは大事。2009/07/10