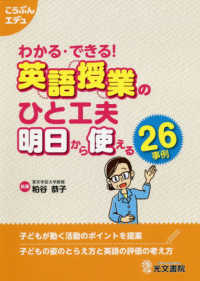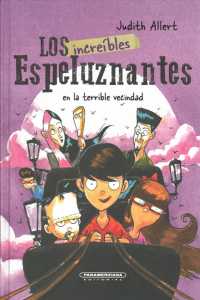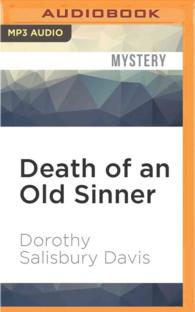出版社内容情報
社会問題化する日本人の「貧困」。「福祉」の観点で語られがちな問題を、日本の経済活動への影響などから分析。
日本の相対的貧困は、およそ2000万人――。75歳以上の後期高齢者よりも多いこの国の貧困層は、この先3000万人まで増えるとも言われています。そしてこの病巣は静かに、けれども急速に、日本に暮らすあらゆる人々の生活を蝕み始めています。
ひとり親、女性、子供…。これまで貧困は、社会的弱者の課題として語られることが多かったはずです。けれど貧困は今や「一部の弱者の問題」として片付けられる存在ではなくなっています。
困窮者の増加が消費を減退させ、人材不足を進め、ひいては国力を衰退させる――。
経済記者が正面から取り組んで見えてきたのは、貧困問題が日本経済や日本社会に及ぼす影響の大きさでした。「かわいそう論」はもう通用しません。求められるのは、貧困を「慈善」でなく「投資」ととらえ直す視点の転換です。企業やビジネスパーソンにできることは何か。貧困を巡る日本の現状と課題、そして解決の糸口を「経済的観点」から分析した初のルポルタージュ。
◆課題編
【1章】統計データが示す現状 普遍化した生活困窮
ネットカフェに6年超 都心に生まれた新しいイエ/介護と非正規雇用で困窮/データが示す貧困リスクの拡大/生活保護費は4兆円/生活保護の受給者が暮らす場所/トイレの窓から逃げた/福祉のあるべき姿とは/「知らないことが議論を阻んでいる」/刑務所の“目的外利用”が映すもの
【2章】貧困を生みだすもの ――(1) “教育ゲーム”が将来を奪う
子供の希望を壊したくない/高い教育費の私的負担/奨学金で自己破産/「大卒のデメリット」/現場労働の軽視が招くツケ
〔インタビュー〕日本学生支援機構 遠藤勝裕理事長
「学生の借金1兆円」が映す、この国の歪み
【3章】貧困を生みだすもの ――(2) 女性と家族を巡る軋み
託児所なんて、ずっと前から当たり前/シングルマザーの専用シェアハウス/育児で狂った、夫婦の歯車/家族か、経済的な自立か/「子供がいることを幸せと思えない」/母に言われた「あんたがいなけりゃ」/2度の妊娠、中絶/なくなった憧れ/未知の「家族体験」
〔インタビュー〕一般社団法人「Colabo」 仁藤夢乃代表
「福祉行政は風俗産業に敗北している」
◆改革編
【4章】“貧困地区”の挑戦 日本最大の「ドヤ街」が「先進地域」に
「1周遅れで先頭を走る」/貧困地区が培った支援力/生まれ変わる街、全国のモデルへ/東京都足立区、悪平等に挑む/教室に響いた「分かった!」/公教育の最大の目的は学力保障/高校中退を防げ/貧困対策は「街づくり」そのもの
〔インタビュー〕滋賀県野洲市 山仲善彰市長
「困窮者自立支援法」モデル都市からの提言
【5章】企業ができること 「貧困投資」はペイする
“最強外資”ゴールドマン・サックスが貧困に投資するワケ/厳密に効果を測定/「貧困投資」の効果/与えるのは「希望の連鎖」/「困窮支援をするのは外資ばかり」/ソーシャル・インパクト・ボンド/スーパーが起こす5日間の奇跡/足かせさえ外せば/積み増された予算/「奨学金、肩代わりします」/仕組みを生んだ“シューカツ”への疑念/「働きやすい職場」と企業の役割
〔インタビュー〕首都大学東京 阿部彩教授
「企業はもう一度、従業員に対する責任を」
【終章】映画『子宮に沈める』が示すもの 「見えないものを見る」意味
密室がもたらす「死」/川崎中1殺害に思う/「もっと違う人の事例がいい」/身近な人の密室に光を当てる
内容説明
後期高齢者よりも多い日本の貧困層。もう、すべての人が貧困問題と無関係ではいられなくなる―。日本の貧困問題を経済記者がレポート。
目次
1章 課題編 統計データが映す現状―普遍化した生活困窮
2章 課題編 貧困を生みだすもの1―“教育ゲーム”が将来を奪う
Interview 日本学生支援機構 遠藤勝裕理事長「学生の借金1兆円」が映す、この国の歪み
3章 課題編 貧困を生みだすもの2―女性と家族を巡る軋み
Interview 一般社団法人「Colabo」仁藤夢乃代表「福祉行政は風俗産業に敗北している」
4章 改革編 “貧困地区”の挑戦―日本最大の「ドヤ街」が「先進地域」に
Interview 滋賀県野洲市 山仲善彰市長「困窮者自立支援法」モデル都市からの提言
5章 改革編 企業ができること―「貧困投資」はペイする
Interview 首都大学東京 阿部彩教授「企業はもう一度、従業員に対する責任を」
終章 映画「子宮に沈める」が示すもの―「見えないものを見る」意味
著者等紹介
中川雅之[ナカガワマサユキ]
日本経済新聞社記者。1982年生まれ。千葉県出身。2006年神戸大学文学部卒業、同年日本経済新聞社に入社。消費産業部で流通・サービス業などを担当。2012年から2015年3月まで日経BP社に出向、『日経ビジネス』記者として主に流通業界を担当。2015年4月から日本経済新聞社企業報道部(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nyaoko
ヒデミン@もも
壱萬参仟縁
onasu
ヒデミン@もも