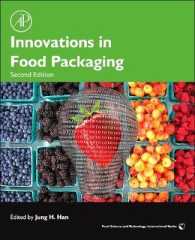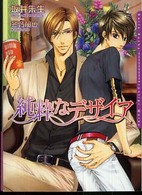出版社内容情報
マクロ経済学者の手による連作短編小説の形式を取り入れた日本経済論。「経済学のロジックと現実経済のデータからいっさいずれていないフィクション」の試み。
本書「最初に編集者から読者へーー「経済学小説」の誕生」から冒頭部分抜粋
あのころ、おそらく2014年の初めごろだったと思うが、私は、小さな出版社の編集者として最大の危機に直面していたのかもしれない。我ながら不覚であった。戸独楽戸伊佐(とこま・といさ)先生から原稿ファイルの入ったメモリーをお預かりしてのち、先生との連絡がまったくとれなくなってしまったのである。
先生の奥様によると、「編集者と会ってくるよ」といって家を出られたそうである。その日、私は、駅の近くの喫茶店で(実は、フランス語で隠れ家の意味である「ルフュージュ」以外で、先生と会ったことは一度もなかった)、確かに先生から原稿ファイルを受け取った。その後、先生は、忽然と私の前から姿を消してしまわれた。私は、先生が、その喫茶店の近くにお住まいだと勝手に想像していたが、実際は、どこにお住まいだったのか、まったく知らなかった。ただ、いたって元気な奥様は、受話器の向こうで「戸独楽は、おりませんが…」と、妙に余韻のある言い回しで、なんだか、「主人だったら、おりますが…」というようにも聞こえた。
【著者紹介】
1960年愛知県生まれ。京都大学経済学部卒。マサチューセッツ工科大学大学院博士課程修了(Ph.D.)。住友信託銀行調査部、ブリティッシュ・コロンビア大学経済学部助教授などを経て、現在、一橋大学大学院経済学研究科教授。2007年に日本経済学会・石川賞、2010年に全国銀行学術研究振興財団賞を受賞。2014年春、紫綬褒章受章。著書に『新しいマクロ経済学』(有斐閣)、『金融技術の使い方・考え方』(有斐閣、2001年日経・経済図書文化賞)、『先を見よ、今を生きよ』(日本評論社)、『資産価格とマクロ経済学』(日本経済新聞社、2008年毎日新聞エコノミスト賞)、『成長桎梏の経済学』(勁草書房)、『競争の作法』(ちくま新書)、『原発危機の経済学』(日本評論社、2012年石橋湛山賞)、『父が息子に語るマクロ経済学』(勁草書房)、『震災復興の政治経済学』(日本評論社)。編著に『震災と経済』(東洋経済新報社)ほか。
内容説明
“失われた20年”と“15年デフレ”という迷妄を「実証」で吹き飛ばす。経済学と小説の“新結合”による渾身の日本経済論。
目次
1 “定常”の中で市民として
2 “定常”の中で公僕として
途中で編集者から読者へ―「あなたが戸独楽先生ですか?」
番外篇
著者と編集者から読者へ―『経済学小説』を真に役立てるために
番外の番外 賃上げとは?―ある左派政党幹部の鬱病(?)
最後に編集者から読者へ―「夜がけっして訪れることのない黄昏」の可能性
著者等紹介
齊藤誠[サイトウマコト]
1960年愛知県生まれ。京都大学経済学部卒。マサチューセッツ工科大学大学院博士課程修了(Ph.D.)。住友信託銀行調査部、ブリティッシュ・コロンビア大学経済学部助教授などを経て、一橋大学大学院経済学研究科教授。2007年に日本経済学会・石川賞、2010年に全国銀行学術研究振興財団賞を受賞。2014年春、紫綬褒章受章。著書に『新しいマクロ経済学』(有斐閣)、『金融技術の使い方・考え方』(有斐閣、2001年日経・経済図書文化賞)、『先を見よ、今を生きよ』(日本評論社)、『資産価格とマクロ経済学』(日本経済新聞社、2008年毎日新聞エコノミスト賞)、『成長桎梏の経済学』(勁草書房)、『競争の作法』(ちくま新書)、『原発危機の経済学』(日本評論社、2012年石橋湛山賞)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yyrn
takao
SQT
yuki
ちくわ