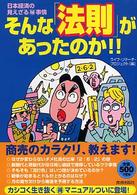内容説明
企業再生の指針、リーン生産からリーン・エンタプライズへ…今の苦しい状況から脱却するには、日本企業は日本人自身が作り上げた思考(私たちがリーン思考と呼ぶもの)にもっと耳を傾け、日本経済のあらゆる方面に適用しなければならない。本書でその方法を解説する。
目次
第1部 リーンの原理(リーン思考とムダ;価値;価値の小川 ほか)
第2部 リーンへの飛躍―思考から行動へ(シンプルなケース;より難しいケース;試金石 ほか)
第3部 リーン・エンタプライズ(小川には溝を、溝には谷を;完全性を夢見る)
著者等紹介
ウォーマック,ジェームズ・P.[ウォーマック,ジェームズP.][Womack,James P.]
リーン・エンタープライズ協会会長。ハーバード大学で修士、マサチューセッツ工科大学(MIT)で「日本、ドイツ製造業比較研究」により博士の学位取得。MITの常勤研究員として米国企業のマルチクライアント方式によるジャパンプログラムなどに参画。現在、非営利団体である同協会においてリーン思考の普及、教育学動等を行っている
ジョーンズ,ダニエル・T.[ジョーンズ,ダニエルT.][Jones,Daniel T.]
リーン・エンタープライズ・アカデミー会長。英国ウェールズのカーディフ大学経営大学院で2001年までリーン・エンタープライズ研究センター長。欧州企業のリーン思考普及、教育活動を行っている。欧州、英国の製造業のための各種委員会の委員を務める
稲垣公夫[イナガキキミオ]
2002年1月から、電子機器受託製造サービス(EMS)の大手企業であるジェイビルサーキットの日本法人、ジェイビルサーキットジャパン(株)社長。25年にわたりNEC本社およびNECアメリカに勤務し、NECアメリカの経営企画部長兼副社長を務める。東京大学工学部精密機械工学科卒業。ミシガン大学大学院で生産工学およびオペレーションズ・リサーチを専攻し、修士号取得
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よく読む
mkt
seura
Kiyoshi Utsugi
ataka
-

- 電子書籍
- まったく最近の探偵ときたら【分冊版】 …
-

- 和書
- 政治分析から政治改革へ