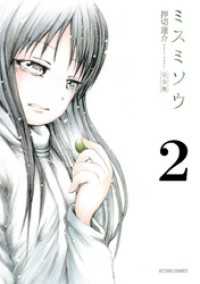出版社内容情報
社員、株主、社会に支持されるリーダーになるには。
その全ての条件をまとめた必読書。社員、株主、社会に支持されるリーダーになるには。
その全ての条件をまとめた必読書。
新規事業、人材育成、株主対話……
長期成長の要諦を語り尽くす
本書は、オリックス シニア・チェアマンである宮内 義彦氏がオリックスグループでの長年の経験から、企業運営の在り方を様々な角度から考え、企業経営論としてまとめた書籍です。
激動する世界情勢や経済状況、次々と生み出される新技術など、現在の社会環境を踏まえた上で、特に新規事業や人材育成、株主対話と言った項目に重点を置き、長期成長のために企業があるべき姿を探ってみました。
安定的な組織の成長は、社員の仕事の幅を広げたり、働きがいを高めたりすることはもちろん、取引先との良好な関係を通じた新しい価値の提供、さらに地域社会への貢献と幅広い成果をもたらします。
そのためには日々、どんな事を考えて、実践していけばよいのか。人材や組織、技術など多様な観点からその条件をまとめています。
宮内氏は、オリックスの経営者として、リース事業から始めて、その後、施設運営やエネルギー事業など様々な新事業を展開、企業価値を高めてきました。
それを通して、著者は「経営とは、目的が明確な組織である限り、原則同じ考え方が通用する」との思いを強くしています。
社員(個人)がどんなに頑張っても、経営者の戦略や指示がずれていては、集団として成果を出せません。一方で、どんなに立派な経営方針を掲げても、社員が努力や団結をしなくては、達成は難しい。
社員が仕事に打ち込み、会社(組織)としても利益を出して、社会に評価される。そうなるための「経営詳論」として、「読者の成功」への思いが本書に込められています。
はじめに
●序章 規模や業種で異なる経営手段
・中長期で成長する条件
【第1部】経営者の言動が会社を決める
●第1章 会社の役割と求める人材
・知識集約型社会の組織作りを
・多様な人材が成功のカギ
・雇用形態も複線型に
・大量リストラではなく、日々リストラを
・「会社は誰のものか」、ステークホルダーの役割
・米ウォール街の発想と決別しよう
・「パナマ文書」が語る社会の意識
●第2章 経営者にしかできない仕事とは
・トップは5年先を見据えよう
・組織は円錐型で運営を
・社長は“経理部長”ではない
・感性を研ぎ澄ます
●第3章 情報発信力を磨いていますか
・報道内容は“アンコントローラブル”
・深いメッセージは届きにくい
●第4章 後継者育成に王道なし
・ベストを尽くしても、結果は分からない
・「万が一」と「バトンタッチ」を区別する
・時代の変化を考慮に入れる
・経営トップ選びは「アートの世界」
●第5章 企業の真の社会貢献とは
・社会の経済部門を受け持つ存在
・企業活動と市場経済、資本主義の今
【第2部】マネジメントの実践
●第6章 誰もが納得する評価制度はない
・たこつぼ組織は必ず滅びる
・リーダーは人間性を磨こう
・混在期にある評価制度
・会社の慣行に沿った仕事は終わり
●第7章 売上高を増やしても、会社は伸びない
・仮想資本金で事業部をチェック
・財務センスを磨く
●第8章 意味ある経営計画を作っていますか?
・一番上にいることを意識
●第9章 新規事業は参入より撤退戦略を
・「いつストップをかけるか」が大切
・5年先を語るより、離陸の見守りを
・成功のポイントは情熱にあり
・「面白いこと」に商機あり
・ずっと“大企業”にはならない
・小箱を一つずつ作る
●第10章 社長、会長、CEO……責任体制を明確に
・“糖尿病”にかからない会社に
・CEOの執行能力がすべて
・ガバナンスは透明性より納得性
●第11章 会社の価値を決めるのは投資家ではない
・企業の価値は社会の評価で決まる
・株主の意見はどこまで聞くべきか
・個人株主に長期保有促す
・ステークホルダー型企業統治へ
●第12章 M&Aは“一目惚れ”に注意
・買収完了がゴールではない
・産学連携の時代に
・永続する企業の創り方
●第13章 失敗が判断力を養う
・内弁慶では勝ち続けられない
・社交の場ではエンターテイナーに
●第14章 マクロを読み誤ると会社は倒産
・日本から世界潮流を読む
・政府も間違うことがある
●第15章 AI、ビッグデータ……技術を見極める
・ハイテクは商品にあらず
・自動車と金融の変化をウオッチ
●第16章 ライバルを意識したらおしまい
・利用者主体の発想を
・「業界初」「業界トップ」の落とし穴
・顧客の言葉はうのみにしない
おわりに
宮内 義彦[ミヤウチ ヨシヒコ]
内容説明
「経営の課題や悩みに突き当たった時に手に取りたい」。社員、株主、社会に支持されるリーダーになるには。その全ての条件をまとめた必読書。新規事業、人材育成、株主対話…長期成長の要諦を語り尽くす。
目次
第1部 経営者の言動が会社を決める(会社の役割と求める人材;経営者にしかできない仕事とは;情報発信力を磨いていますか;後継者育成に王道なし;企業の真の社会貢献とは)
第2部 マネジメントの実践(誰もが納得する評価制度はない;売上高を増やしても、会社は伸びない;意味ある経営計画を作っていますか?;新規事業は参入より撤退戦略を;社長、会長、CEO…責任体制を明確に;会社の価値を決めるのは投資家ではない;M&Aは“一目惚れ”に注意)
第3部 永続する企業の創り方(失敗が判断力を養う;マクロを読み誤ると会社は倒産;AI、ビッグデータ…技術を見極める;ライバルを意識したらおしまい)
著者等紹介
宮内義彦[ミヤウチヨシヒコ]
オリックスシニア・チェアマン。1935年神戸市生まれ。58年関西学院大学商学部卒業。60年ワシントン大学経営学部大学院でMBA取得後、日綿実業(現双日)入社。64年オリエント・リース(現オリックス)入社。70年取締役、80年代表取締役社長・グループCEO、2000年代表取締役会長・グループCEO、03年取締役兼代表執行役会長・グループCEOを経て、14年シニア・チェアマン就任。これまで総合規制改革会議議長など数々の要職を歴任。現在、(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あすなろ@no book, no life.
所沢
Splash
Yusuke Nakamura
fuku