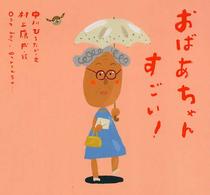出版社内容情報
『そういうことだったのか!』
知ってるようで意外と知らない日本初の武家政権誕生に迫る!
学校の授業で歴史を習うときに必ず出てくる「鎌倉幕府」。日本で初めて本格的な武士による政治のはじまりとして覚えさせられた方も多いことでしょう。そこで、習った方には思い出していただきたいのですが、鎌倉幕府の成立は何年と教わったでしょうか?
①イイクニつくろう鎌倉幕府の1192年
②イイハコつくろう鎌倉幕府の1185年
③イイヤヲはなとう鎌倉幕府の1180年
④その他
おそらくすでに成人されて久しい方は①の1192年で習っており、
若い世代や今まさに教科書で習っている方は②の1185年だという人が多いのではないでしょうか。
あるいは教えている先生によっては③の1180年や④のそれ以外の年数で教えていらっしゃるかもしれません。
このように、誰もが勉強してきたはずの事柄であっても、調査や研究で変わっていくのが歴史です。
歴史は、現在から過去を発掘して調べることで知識が増えるものですが、古くなればなるほど「これは絶対だ!」と確信できるものが少なくなっていきます。そのため、新たな発掘や発見により従来の定説が覆ることがあります。同時に、古い時代になるにつれ、徐々に推測や想像の部分が増えていくことになります。
そしてこの鎌倉幕府の時代。
この時代は、だれにも程よく想像力を広げる自由があたえられています。
近世以降と違って、信頼できる史書・文献が限られているからです。また、その記述内容にも幅があり、一様ではありません。
歴史家によっても、解釈・見解は大きく異なります。
かといって、神話に頼らざるを得ない古代ほど、見通しが利かないわけではありません。
真相が判らないゆえの陰謀論もいくつか唱えられていますが、それを頭から否定できる、あるいは肯定できる史料が少ないことは、むしろこの時代の大きな「魅力」になっています。
さて、武士による政治と聞くと、その武力を背景にした暴力的な政治を想像してしまいがちです。しかし、鎌倉幕府が成立したころ、そうした想像とは似つかわしくない「合議制」が導入されました。「合議」とは、現代では「二人以上が集まって相談すること」を指します。
つまり鎌倉幕府の武士たちは、力ではなく話し合いによる政治を目指したのでしょうか?
もしそうなら、これは現代まで続く議会政治のはじまりということなのでしょうか?
本書が微力ながらお手伝いしますので、これまで明らかにされてきた歴史と、欠落を埋める想像力を働かせながら、この時代に思いを馳せてみませんか?
内容説明
2022年は“もののふ”が熱い!明治維新以前の日本大変革!武士の政権はなぜ鎌倉で樹立して「合議制」をはじめたのか?現代風の解説やイラストで当時の状況や人物たちを生き生きと描く!歴史モノの作品やドラマもこの1冊でより楽しめる!
目次
プロローグ 無法地帯?東国の夜明け
第1章 「鎌倉殿」が誕生するまで(武士が中央政界に進出するまで;「鎌倉殿」の不遇な流人時代;平氏追討にいざ出陣!;「鎌倉殿」の誕生)
第2章 幕府の完成と合議制の開始(盛者必衰の理、平氏の滅亡;鎌倉軍事政権の完成;「要塞都市」鎌倉の誕生;2代目「鎌倉殿」の誕生)
第3章 2代目「鎌倉殿」と合議制の13人(2代目「鎌倉殿」と合議制の成立;宿老13人のプロフィール;13人合議制の崩壊)
第4章 新しい「鎌倉殿」姉弟の時代(“仁義なき戦い・鎌倉死闘編”の行方;つかのまの平穏から和田合戦へ;マルチな上皇と3代目「鎌倉殿」;承久の乱と尼将軍)
エピローグ 「法の下」の武家政権
著者等紹介
大迫秀樹[オオサコヒデキ]
編集・執筆業。「広い視野で、わかりやすく」をモットーに、教養・雑学書の企画から執筆まで幅広く関わる。主なジャンルは、歴史・地理・時事・文章術など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
夜明けのランナー
だてこ
ナツ
KIYO
m