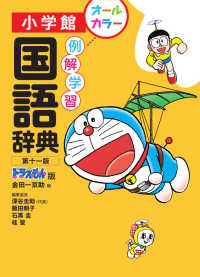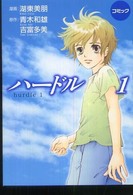出版社内容情報
価値あるもうひとつの文学史
★明治・大正文学状況のなまなましい息吹を伝える。
★当時の文学の史的体系をめざした。
★現代の自閉的な作品論から自らを解放させうる文学史の宝庫。
「明治大正文学史集成」全12巻
平岡敏夫(筑波大学名誉教授)監修・解説 揃本体103,000円+税
1 日本文学史(上巻)
三上参次・高津鍬三郎共著 本体9,000円+税
A5判/函入/金港堂版/明治23年発行/原・菊判
★内容★文学史とは何ぞ/日本文学の起源及び発達/奈良朝の
文学/平安朝の文学/他
2 日本文学史(下巻)
三上参次・高津鍬三郎共著 本体10,000円+税
A5判/函入/金港堂版/明治23年発行/原・菊判
★内容★鎌倉時代の文学/南北朝及び室町時代の文学/江戸時
代の文学/他
3 明治文学史
大和田建樹著 本体6,000円+税
A5判/函入/博文館版/明治27年発行/原・四六判
★内容★謂はゆる輸入時代/謂はゆる反動時代/謂はゆる新聞
時代/他
4 時代文学史
高橋淡水著 本体6,000円+税
A5判/函入/開発社版/明治39年発行/原・四六判
★内容★総論/明治の新聞雑誌/明治の散文/明治の小説/明
治の新体詩/明治の少年文学/明治の短歌/明治の俳句/他
5 増補 明治文学史
岩城準太朗著 本体9,000円+税
A5判/函入/育英社版/明治42年発行/原・菊判
★内容★前代継承の文学/新文学の先駆/新文学思想/新文学
の勃興/文学の転進/文学一転の機/新興文学の由来/他年表
6 明治小説文章変遷史 明治小説内容発達史
明治文学変遷史講和
A5判/函入/文学普及会版/原・四六判 本体7,500円+税
徳田秋声著(明治小説文章変遷史)/大正三年発行
田山花袋著(明治小説内容発達史)/大正三年発行
島村抱月著(明治文学変遷史講和)/大正四年発行 以上合本
7 近代文芸史論
高須梅溪著 本体10,000円+税
A5判/函入/日本評論社出版部版/大正10年発行/原・四六判
★内容★現代文芸の大勢及び進歩/英米功利思想の流入と啓蒙
運動/翻訳文学と政治小説の流行/ロマンチシズムの時代/他
8 明治大正 新文学史観
小島徳弥著 本体14,500円+税
A5判/函入/教文社版/大正14年発行/原・四六判
★内容★啓蒙運動と新文学の曙光/明治文学の爛熟と浪漫主義
の運動/自然主義文学の全盛時代/非自然派小説と新浪漫主義
的傾向/混沌たる大正文学界への展望/明治大正文学年表/他
9 明治大正の国文学
岩城準太朗著 本体6,000円+税
A5判/函入/成象堂版/大正14年発行/原・四六判
★内容★新文学建設の主張/西洋文学の影響/新体詩界の曙色
/小説界の進境/近代文学の樹立/口語体文章の創始/他
10 明治大正文学の輪郭
加藤武雄著 本体5,000円+税
A5判/函入/新潮社版/大正15年発行/原・四六判
★内容★軟派文学と政治小説/自然主義的傾向/白樺派の諸作
家/プロレタリヤ文学運動/明治大正文芸研究資料/他
11 私の見た明治文壇
野崎左文著 本体10,000円+税
A5判/函入/春陽堂版/昭和2年発行/原・四六判/狂歌一
夕話/他
12 自己中心 明治文壇史
江見水蔭著 本体10,000円+税
A5判/函入/博文館版/昭和2年発行/原・四六判
監修のことば 平岡敏夫
「本邦文学史の嚆矢」とうたった三上参次・高津鍬三郎
『日本文学史』(上下)が出たのは明治二十三年十一月のこ
とであるが、実は同じ年の四月に関根正直『小説史稿』が
出ていて、北村透谷が「文学史の第一着は出たり」の一文
で同書を鋭く批判したことは知られている。しかし、三上
・高津のそれが書名にも「文学史」を名乗った最初の体系
的文学史叙述であることは動かず、その「緒言」や文学史
とは何ぞと問いかけた「総論」は今日においても多くの示
唆をふくんでいる。
同書は近世までの叙述であるが、右のような見地からこ
の「文学史」を冒頭におき、以下、明治・大正期に刊行さ
れた明治・大正文学史を選び、十巻として集成してみた。
一見、古色蒼然たる明治大正文学史を今日復刻する意味
はどこにあるのか。これらが古色蒼然としか眼に映らぬと
したら、そこにこそ、このような文学史集成が編まれねば
ならぬ理由があると言えよう。
明治・大正期の史家がとらえた作家・作品は、実は今日
のステロ化された図式から見れば意外に新鮮であり、思い
がけなく新しい視点を供給してくれる。彼らは文学史叙述
という自己の体系のなかに、同時代、あるいはすぐ前の時
代の文学を主体的に位置づけているのである。
木を見て森を見ざる研究志向や自閉的な作品論から自身
を解き放つためにも、今日もはや容易に入手しがたいこれ
らの文学史は宝庫と言ってよく、いま読み返しても興味し
んしんたるものがある。附録の二巻もすでに稀観本であり、
復刻の意味はきわめて大きいものと信じる。
方法論と個別研究の集成
近代文学研究者 長谷川 泉
一国文学史は、方法論と個別研究の集成である。
文学史の方法論は、種々の論議があるが、いかにすぐれ
た方法をもってしても、個別の研究の成果に支えられなけ
れば、文学史の実りは期待できない。
個別の研究には、作家・作品の研究、主義・流派・思潮
の研究などがあり、その充実によってすぐれた文学史は構
成される。
日本の文学史は、明治期以降、西欧文学の摂取によって
大きく転換した。故に、明治・大正期の文学の史的把握が
どのようになされたかということは、巨視的な日本文学史
の中でも注目をひく。この企画の焦点はそのようなところ
にあると思う。
日本文学の史的把握は、アストンの「日本文学史」(近
代は入っていない) いらい、最近のドナルド・キーンの
「日本文学史」(近代も入る) にいたるまで、外国の研究
者にも関心を呼んでいる。そのような世界的視圏の裡で注
目されている日本文学の史的把握の大きな転換期を、先人
がどのように定着したかということを跡づける意義は大き
い。
方法論も、個別研究の成果も、一望のもとに視野に入っ
てくるからである。
『明治大正文学史集成』を推す
東京大学教授 三好行雄
明治・大正期に刊行された文学史を全十巻に集成して復
刻するという、つとに独自の文学史像を主張する平岡敏夫
氏を監修者に得て、まことに時宜を得た好企画だと思う。
あるいは、なにを物好きなという声も聞こえるかもしれ
ない。確かに、もっとも長い声名をほこった岩城準太郎氏
の著書でさえ、研究史からその名が消えてすでに久しい。
しかし、もちろん、忘れられているということと、無価
値であるということは別である。
同時代の文学に史的整理を与える試みには、さまざまな
困難がつきまとう。根本的には、歴史が歴史として成りた
つための時間の距離の不足は否めず、だから、後代の遠近
法はそれらの業績をやすやすと乗りこえていったように見
える。しかし、ことを裏返していえば、本集成に収められ
た文学史はいずれも、同時代の文学状況のなまなましい息
吹きを確実に体験した著者たちが、それらと主体的にかか
わりつつ史的体系をめざした格闘の所産であって、現代か
らは見えにくい時代のエトスやパトスが再現されている。
動態としての文学をどう体系化するか、という問いの原
点にほかならない。
本体系を通読することで、ひとは、近代文学史が登りつ
めていった階梯を辿ることができると同時に、個々の方法
・史観・価値判断などを通じて、現代においてなお新しい
発見にみちびかれるはずである。それに学ばないのは、む
しろ後代の怠慢というべきであろう。
〈いずれも発刊時のことばより〉