- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 図書館・博物館
- > 図書館・博物館学一般
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
45
図書の分類は番号で。しかし各番号には偏りがある。ふだんから不思議に思っていたことが、やっぱりそうか、みたいな形ではっきりと述べられているので、図書館関係者の思うことと、利用者の思うことは、実はそんなに変わらないことに納得。そりゃそうだよね。「913.6」という番号を聞いて、すぐにピンとくる人にこそ、この本はおすすめである。本という世界が、実は個人の興味・関心をはるかに越えて広いのだ、ということがよくわかる。だからこそ、この「読書メーター」に見える、ひとつの傾向も、しごく当たり前なのである。2015/03/20
アセロラ
7
NDC(日本デシマル・クラシフィケーションの略、日本十進分類法のこと)をよく知らない私にとっては新発見の連続でした。0類から9類まで順にどのような本が分類されているのか説明があり、それぞれの分野で著者が読んだ本も紹介されています。また、図書館によって、とある本が違う分類をされてる場合や、分類に疑問を持つこともあるそうです。なるほど、そういう見方で読書するのもおもしろいんですね。100哲学の分類で、104〜108は内容に関わらず、形式による分類だそう。よくわからないのですが、図書館で見ようと思います。2019/07/28
海星梨
6
シリーズとしては、図書館学と一般の人々をつなぐもののようだが、実際に筆者が読んだ本の紹介でNDCをみていくという構成で、内容が薄く「われわれ高齢者」ときたり筆者(男性高齢者)視点からの説明のみで、二十代女性としてはウンザリしてしまった。本の形をしているものの、草案以下の文章で、図書館界の人手不足が如実に分かる。かねてからの疑問「350統計とは?(統計の出し方は数学に分類されており、実際の統計は何の統計かに基づいて分類されている気が)」は「340財政、350統計は飛ばして」などと納得がいかない。2019/08/26
キリル
6
数字という記号で表されてどうにもとっつきにくい図書分類を、その分類にどんな本があるのか紹介することで分かりやすく説明されている点がよいと思います。分類を見ていると確かになんでここにあるのかというものもあるし、そういうところにツッコミがあったので共感できて面白かったです。2016/05/29
hyoshiok
5
この本面白い。図書分類(日本十進分類法)に従って0類(総記)から始まって、哲学・宗教(1類)、歴史・地理(2類)などなどすべての分類に渡って本を紹介していく。分類の細かさがかなり恣意的で宗教が神道(170)、仏教(180)、キリスト教(190)と3つしか大項目がないとか、わかって面白い。読書ガイドとしても楽しい。自分は自然科学(4類)はよく読むので馴染みがある。2017/05/28
-
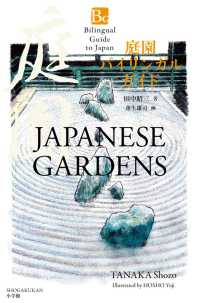
- 和書
- 庭園バイリンガルガイド




