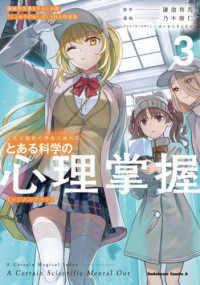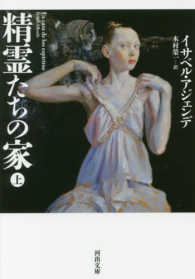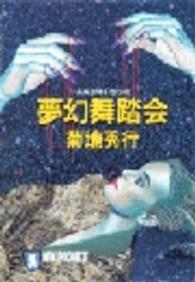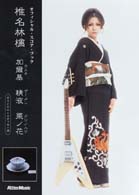内容説明
いま決めなければ生き残れない!やわらかな語り口で最新研究を紹介しながら、通説にも疑問符!歴史家による実情の読み解きで、真実の日本史が見えてくる。
目次
あの兵力差で信長は本当に桶狭間を戦ったか
「天下統一」という新概念はどう生まれたか
部下・光秀が「本能寺」を決めた出来事
「戦国最強の武将」は誰か
武将たちが残した人生哲学
執権北条氏、粛清政治の手法―戦国前夜1
「大義名分」がない中世武士の感覚―戦国前夜2
利休は強欲だから秀吉に殺されたのか
「利休七哲」と徳川大奥
武将の名から人間関係が見える
家康と「信康切腹」と「長篠」
著者等紹介
本郷和人[ホンゴウカズト]
東京大学史料編纂所教授。1960年、東京都生まれ。東京大学文学部・同大学院で石井進氏、五味文彦氏に師事し日本中世史を学ぶ。専門は中世政治史、古文書学。博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
今ごろになって『虎に翼』を観ているおじさん・寺
46
題名からすると一見よくありそうな本ながら中身は実に面白い。書いたのは東大史料編纂所教授・本郷和人。ヤンマガの宮下英樹『センゴク』にも協力している歴史学者だ。信長・秀吉・家康の話を中心に時々鎌倉室町の話になる。平易な文章で通説にもやんわりと水を差す。桶狭間の人数、本能寺の実相、利休切腹の原因、家康の長男切腹の理由。学者の話はやはり作家の推理とは違う。勉強になる。戦国一の戦上手として毛利元就を挙げているのが広島人の私には嬉しい。東大史料編纂所所蔵の肖像画(模本)が沢山収録してあるのも良い。お勧め。2015/06/10
ホークス
28
2015年刊。著者は大河ドラマ「平清盛」で時代考証を担当。既存の仮説に縛られず文献を再読し、柔らかい発想で歴史を考える。鎌倉時代の「守護」は権威がある反面、現地の支配力は弱い。国人(在地武士)を率いる「守護大名」は室町時代に現れる。守護のイメージが鮮明になった。行政は国人が担っていたので、戦国大名は国人の意向に振り回される。織田信長の新しさは、国人の下で村落を支配する「地侍」まで指揮下に入れた所。姓(かばね)、家名、「いみな」の解説が丁寧で、理解が深まったのが嬉しい。ちょっと真偽の怪しい話も含めて面白い。2020/07/27
謙信公
18
産経新聞連載「日本史ナナメ読み」の新書化。桶狭間の戦いの真相、天下統一を「発明」した信長、本能寺の変の光秀の心の内、家康と信康切腹と長篠の戦いの関係などの興味深いテーマを、やわらかな語り口で、最新の研究を紹介しながら通説にも疑問符をつけて紐解いていく。「家名」「役職名」「かばね(姓)」「いみな(諱)」「法名」そして「通称」の豆知識や北条政子にみるフェミニズムの歴史観、大島優子がでてきたりなど、バラエティに富んで面白い。戦国武将といいつつ、次年度の大河ドラマの関係か、鎌倉時代が2章設けられているのはご愛嬌。2025/04/02
maito/まいと
17
教授らしからぬ穏やかな書き口調なのだが、指摘しているポイントは結構盲点、それでいて論理構成はとっても冷静貫徹、と本郷さんの魅力満載の1冊。若干食い足りないところがあるものの、あまり話題にのぼらない素朴な疑問こそ、これからの日本史を読み解くのに必要なんだ、という(結構)熱いメッセージが込められているような気がする。日本史苦手な方でもふむふむと読み進められるので、気軽に読んで欲しいなあ。2015/06/28
クサバナリスト
15
本郷さん、ご自分の大好きなAKB48メンバ-を例にとる解説など、学者らしからぬ解説は良いのだが、本郷さんの年齢を考えると読者が離れるかもと余計なお世話か?武将名の解説や色んな人の親族関係は興味深かった。2015/08/21