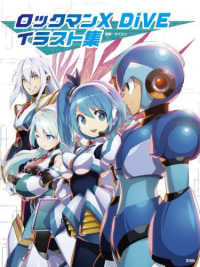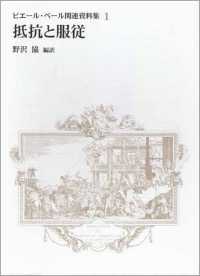内容説明
福澤諭吉はなぜ西相模にこだわったのか。交詢社を媒介として地域の開発とリーダーの育成を提唱・指導しつつ相模の美酒に舌づつみをうつ知られざる諭吉像を描く。
目次
序―諭吉はなぜ西相模に着目したのか
1 足柄県のリーダー柏木忠俊に意気投合した諭吉
2 交詢社に托した諭吉の「もう一つの国家」への夢
3 「近代」づくりを西相模の水脈に求めて
4 諭吉起草の「国会開設建言書」と相州自由民権家
5 諭吉が愛でた丹沢の美酒と西相模を徘徊して
6 長谷川彦八の東相模のリーダーとしての資質
著者等紹介
金原左門[キンバラサモン]
昭和6年(1931)静岡県浜松市生まれ。昭和29年(1954)東京教育大学文学部社会科学科卒業。同大学大学院博士課程を経て昭和38年(1963)中央大学法学部講師、昭和45年教授。平成13年(2001)中央大学退職、名誉教授。『「近代化」論の転回と歴史叙述』中央大学出版部、平成11年、同年度政治研究櫻田会賞特別功労賞受賞。『日本近代のサブ・リーダー』日本経済評論社、平成17年、同年度風光る賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 【フルカラー】インキュバスだって純愛し…
-

- 電子書籍
- 元カノの弟が可愛いって話 1巻 トレイ…