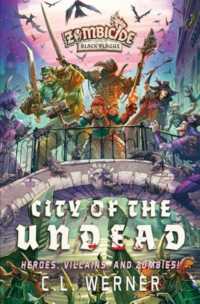内容説明
失敗学では、動機的原因と不具合事象の関係を「ワナ」あるいは「失敗のカラクリ」と呼ぶ。最終的に起こる不具合事象はさまざまであるが、人間がハマるワナは業種や職種にかかわらず同じで、そのワナの種類はそれほど多くはない。だからこそ、過去に経験したワナや他分野で明らかになったワナから、自分野での未然防止ができるのである。前著『失敗学と創造学』で大反響を呼んだ著者が、さらに進化した実践的ノウハウを公開する。
目次
第1章 重要な基本的考え
第2章 失敗学のエッセンス
第3章 失敗学のエッセンスのフレームワーク
第4章 フレームワークの重要ポイント
第5章 今までの原因分析と対策は間違っていた
第6章 失敗のイメージ図
第7章 「よく見かける分析」と「失敗学を使った分析」の比較
第8章 他の分析手法との比較
第9章 いい加減に使われている言葉
第10章 論理性のトレーニングのすすめ
著者等紹介
濱口哲也[ハマグチテツヤ]
東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻社会連携講座特任教授。株式会社濱口企画代表取締役。1960年生まれ。1986年、日立製作所中央研究所入社、磁気ディスク装置の研究・開発・設計に従事。1998年、東京大学博士(工学)。2002年、東京大学大学院工学系研究科産業機械工学専攻助教授。2007年、同大学同専攻社会連携講座特任教授、2015年、株式会社濱口企画代表取締役
平山貴之[ヒラヤマタカユキ]
一般財団法人日本科学技術連盟品質経営研修センター営業・企画グループ主任。1985年生まれ。2008年、日本科学技術連盟入職、研修開発課(現営業・企画グループ)に配属、オンサイトセミナー(出張セミナー)の営業・企画・提案・運営・管理業務に従事。2014年、研修開発課主任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜長月🌙
Tenouji
F_Die02
柞山力哉
あーたん
-

- 洋書
- If I Could