- ホーム
- > 和書
- > 工学
- > 経営工学
- > 品質管理(QC等)標準規格(JIS等)
内容説明
2007年度版を見直し、さらに充実。とくに、ヒューマンエラーに関する事例や製造現場以外の事例を紹介している。
目次
第1章 どこでも、どんなときにでも、真の論理力が求められる時代になってきた
第2章 「なぜなぜ分析」で、真の論理力を鍛えて、職場の基盤を整えよう
第3章 「なぜなぜ分析」に入る前に確認すべき5つのポイント
第4章 「なぜなぜ分析10則」でねらいをはずさず、「なぜ」を展開しよう
第5章 「なぜなぜ分析」の進め方と分析シート
第6章 「なぜなぜ分析」の実践上の注意点
第7章 「なぜなぜ分析」を活用し、職場の基盤を整えていく
著者等紹介
小倉仁志[オグラヒトシ]
有限会社マネジメント・ダイナミクス社長。中小企業診断士。1985年東京工業大学化学工学部卒。同年デュポン・ジャパン(現(株)デュポン)合成樹脂事業本部入社。1992年から(社)日本プラントメンテナンス協会にて、TPM(トータル・プロダクティブ・メンテナンスまたはマネジメント、製造業向け体質改善プログラム)指導に従事。「なぜなぜ分析」のルール化、体系化に取り組み、国内外初の「なぜなぜ分析」に関する書籍を1997年に発刊。その後、2002年に確立した「なぜなぜ分析10則」をさらに改訂し、2009年度版「なぜなぜ分析10則」に至る。2005年に有限会社マネジメント・ダイナミクスを設立・「なぜなぜ分析」に関するセミナー・社内研修(年当たり100数十件)を実施するとともに、実際に発生したトラブルの原因追究を一緒に実施していきながら、内部の問題点を洗い出し、改善を一緒に実施していく、「なぜなぜ分析」を核とした、思考の変革による企業の体質改善の支援を行う。「なぜなぜ分析」の研修においては、製造業全般(自動車部品、電気・電子、石油化学、セメント、医薬品、医療器具、食品、家庭用品、印刷など)、船舶修理、ガス、電力など)で実績がある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
閑居
二階堂聖
ベローチェのひととき
7a
ちょうすけ
-

- 電子書籍
- 偽りの悪女ですが末永く幸せになりましょ…
-
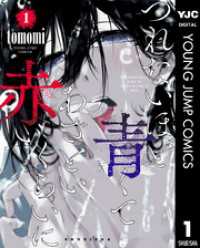
- 電子書籍
- つれないほど青くて あざといくらいに赤…






