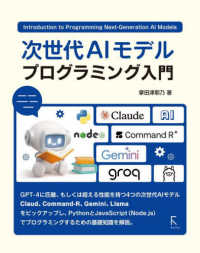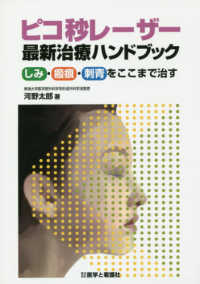出版社内容情報
中・上級編として七福神、十三仏、二十五菩薩から聖徳太子、天井画、昭和大納経口絵へと展開する骨描きを中心にした描法を披露。
松久宗琳[マツヒサソウリン]
大正15年(1926年)、仏師・松久朋琳の長男として京都市に生まれる。幼少より絵画に熱中し、その基礎を学ぶが、病を得て父の許に帰り、仏師としての道を歩む。戦後、父の良き伴侶として、彫造に従事、また37年には京都・九条山に「京都仏像彫刻研究所」を開設するなど、仏像彫刻会に確固たる地歩を築く。39年より「仏教美術展」を主催し、宗教芸術の真髄を示す力作を発表してきた。48年には『仏像彫刻のすすめ』を父と共著、同年「宗教芸術院」を設立し、広く後進の指導にあたってきた。総本山四天王寺大仏師、大本山成田山大仏師。平成4年3月死去。
内容説明
中・上級編として七福神、十三仏、二十五菩薩から聖徳太子、天井画、昭和大納経口絵へと展開する骨描きを中心にした描法を披露して、読者の要望に応える。
目次
第1章 仏画の基本
第2章 七福神の描法
第3章 十三仏の描法
第4章 二十五菩薩の描法
第5章 聖徳太子―襖絵の描法
第6章 四季の花―天井画の描法
第7章 昭和大納経
第8章 参考篇 下図
第9章 作例
付録
著者等紹介
松久宗琳[マツヒサソウリン]
大正15年(1926年)、仏師・松久朋琳の長男として京都市に生まれる。幼少より絵画に熱中し、その基礎を学ぶが、病を得て父の許に帰り、仏師としての道を歩む。戦後、父の良き伴侶として、彫造に従事、また37年には京都・九条山に「京都仏像彫刻研究所」を開設するなど、仏像彫刻会に確固たる地歩を築く。39年より「仏教美術展」を主催し、宗教芸術の真髄を示す力作を発表してきた。48年には『仏像彫刻のすすめ』を父と共著、同年「宗教芸術院」を設立し、広く後進の指導にあたってきた。総本山四天王寺大仏師、大本山成田山大仏師。平成4年3月死去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- DVD
- 心霊曼邪羅36