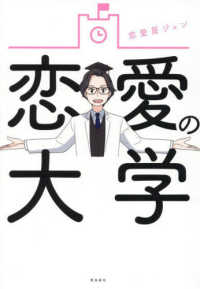- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 図書館・博物館
- > 図書館・博物館学一般
内容説明
書誌を作成し、解題を書く、これは図書館員の基本です。資料を渉猟する、バックグラウンドを読む、構成を考える、スキルを駆使する、解題を書く、なんと冥利につきること!
目次
1章 文献解題ことはじめ
2章 テーマの発見と研究成果の発表
3章 単行書への視点
4章 歴史背景を考察する
5章 文献解題の書き方
6章 専門用語と解題
7章 研究の作法
著者等紹介
平井紀子[ヒライノリコ]
1940年東京生まれ。1960年文化女子大学図書館勤務、司書長。2000年退職。(財)ファッション産業人材育成機構資料室。聖徳大学、亜細亜大学図書館司書講習講師。2004年都留文科大学司書課程非常勤講師。アート・ドキュメンテーション学会会員。『装いのアーカイブズ』(日外アソシエーツ)図書館サポートフォーラム賞受賞ほか論文多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
禿童子
35
「解題」とは聞きなれない言葉だが、一冊の本について、その内容を限られた字数でまとめた要約と理解している。著者の平井紀子さんは服飾関係の著作もある方で、例として挙げられる服飾関連の歴史に関する解題は、それ自体が読者の興味を引く話題に富んでいる。たとえば、17世紀フランスでは最新流行のファッションを広めるためにマネキンに衣装を着せて人力車で引くことが行われ、このマネキンを「パンドラ」と呼んでいた。当時は写真もモード雑誌もない時代。フランス革命の頃もイギリスやドイツなどの交戦国でもパンドラがもてはやされていた。2021/02/27
にきゅ
0
自分の学習のために。利用者の求めていること以上のことを提供できるようになるのでしょうか。自分の専門分野ってないもの。特定のテーマで興味のあることは、複数あるけれど、その道のひとと議論したり、できないものなぁ。2017/08/17
駒子
0
主題を持ってる専門性のある司書向けだと思う。解題作ったり、書誌を調査、研究したりできるのはかなりハードルが高いと感じた。司書だけではなく、研究者が資料を探して文献調査、整理するときにも活用できるのかな、と思った。私は個人で調べものをする者ですが、解題の作り方は活用したいと思いました。2025/01/16