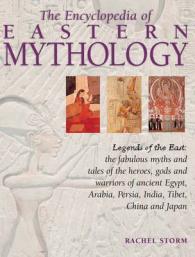- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 図書館・博物館
- > 図書館・博物館学一般
内容説明
幕末から戦後まで図書館に貢献した先覚者たちの活躍を描く、近代日本の公共図書館・大学図書館発展史。日本近代図書館の源流として「博物館からの流れ」「米国公共図書館の無料制からの流れ」「都市型公共施設からの流れ」「新聞縦覧所や地方の読書施設の発展からの流れ」の4つの流れがあることに目をつけ、図書館を巡って織りなす人間模様を克明に描くことで近代日本の図書館を描きだした画期的な書。
目次
第1章 戦前の公共図書館―幕末期から辿る公共図書館の萌芽(日本版大英博物館の創設者―町田久成;市川清流が書籍院建設を建白;田中不二麻呂が東京書籍館を設立 ほか)
第2章 戦後の公共図書館―復興から発展へ(戦後の図書館界の再建;占領軍図書館担当官キーニーの登場;金曜会と図書館改革 ほか)
第3章 大学の図書館―源流から学術情報まで(近代大学図書館の源流;『蕃書調所書籍目録写』と『御書籍目録』「蛮書類」;書房と呼ばれた大学図書館―工学寮・工部大学校の図書館 ほか)
著者等紹介
石山洋[イシヤマヒロシ]
1927年生まれ。1951年東京大学地理学選科卒。国立国会図書館奉職。索引課長、電子計算課長、外国逐次刊行物課長、資料収集担当司書監、同図書館研究所長、1988年退職。東海大学文学部教授、日本文明論、図書館情報学を講じる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。