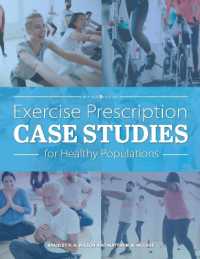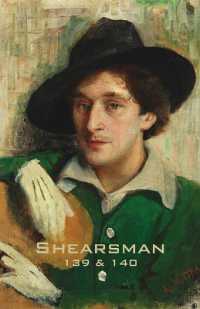内容説明
毒はどのように利用され解明されてきたのか、文化的・歴史的にアプローチする。
目次
第1章 毒と人間の歴史(毒はどのようにとらえられてきたか?;近代科学の発展と毒)
第2章 毒を科学する(毒とは何か?―基本知識とその分類について;毒の侵入と身体への作用)
第3章 毒と人間の危険な関係(規制薬物;毒と兵器;公害の原因tなる毒;放射性物質、放射線、放射能)
第4章 毒をもつ動物や植物(植物の毒;病原性微生物の毒;キノコの毒;魚介類の毒;節足動物の毒;両生類の毒;爬虫類の毒)
第5章 毒の有効利用(生活のなかで利用されている毒;医療に貢献する毒)
著者等紹介
船山信次[フナヤマシンジ]
1951年仙台市生まれ。東北大学薬学部卒業・東北大学大学院薬学研究科博士課程修了、天然物化学専攻。薬学博士。東北大学医学部細菌学教室研究生、イリノイ大学薬学部博士研究員、北里研究所微生物薬品化学部研究員~室長補佐、東北大学薬学部生薬学教室助手~専任講師、青森大学工学部生物工学科天然物化学分野助教授~教授、青森大学大学院環境科学研究科教授(併任)、弘前大学地域共同研究センター客員教授(兼任)などを経て、日本薬科大学教授。日本薬史学会評議員。Pharmaceutical Biology(USA)副編集長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おりん
31
毒について広く浅く、図解で説明してある本。高校生程度の生物・化学の知識があれば十分理解できる。多分中学生の理科の知識程度でも理解はできると思う。毒を歴史的視点から述べている部分は、個人的には新鮮に感じて面白かった。広く浅く述べられているので、毒についての雑学(ムダ知識とも言う)を知りたい僕のような人間の入門書として最適だと思う。2017/11/13
Rie【顔姫 ξ(✿ ❛‿❛)ξ】
27
とても面白かった!毒がどのように捉えられてきたのかの歴史から、その化学的な性質、毒がどのように体内に侵入するか、毒をもつ様々な動植物、そして、医療や生活の中で活用されている毒。毒と言っても、ヘロインやコカインなどの薬物、兵器として使用される化学兵器や生物兵器、公害の原因となる鉱物毒や放射性物質まで幅広く解説されている。図版が豊富でカラフルな本なので、理系でなくても楽しく読める。考えてみると、アガサ・クリスティの本でよく使われているヒ素など、毒は小説の材料としても多く用いられている。続)2021/08/09
うめ
18
気軽な感じで読み始めたら、しっかりばっちりお勉強用。教科書と共に知識を深める為の、まさに図説。だけども後半は化合物の羅列が多く、生体への影響の機序や作用などが割愛されていたのが物足りなかったかな。人の体のシステムの繊細さには感嘆してしまうし、世の中に満ち溢れた物質が簡単にその完璧なシステムを撹乱させてしまう事にも驚く。うん、もっと色々知りたくなる。毒から逃れる事は出来ないから、文化と正しい知識との間で、どう折り合いをつけるかね。勉強て大事◎今後は加工肉と魚介類は一緒に食べない事にする。知識は武器。2015/07/25
姉勤
18
この時期毛虫の毒にやられるので。古代からの人と毒(薬)の関わり。これらを発見するのに、どれだけの人と獣が犠牲になったか。暗号やカメムシの様な分子式には頭が痛くなるが、図解と写真に扶けられ、分かりやすい。スズランなど身近な植物が結構危険だったり、麻薬や食中毒などが人体にどう作用するかの医学的、生物学的な説明も為になった。毒と薬は表裏一体。使い方次第と思う。ただ、身近な物質であるのに、フッ素の危険性に全く触れてなかったり、放射線の危険を謳いつつ劣化ウラン弾の後遺症に懐疑的だったりと、些細なことが気になる性分。2014/05/12
Kouro-hou
15
同じ著者の毒の本が面白かったので、こちらにも手を出してみました。毒を語るには薬は避けられず、薬を語るには医療の歴史から。アルカロイドが人体に影響を及ぼしやすい事を語るのには分子構造式の見方から。ベンゼン環は基礎知識! いや学生時代にこんな本に出会えていたら、もっと化学と仲良くなれていたかもしれません。猛毒サリンを解毒する毒アトロピンのメカニズム解説や各麻薬・麻酔類が神経に及ぼす効果の違い、蛇や蠍の猛毒器官の仕組み、意外と有害物質だらけのフキの正しい下処理などの知識山盛りで為になります。2014/07/17
-

- 電子書籍
- -spinel- Debut OneM…