内容説明
ヨーロッパ世界のもう一つの起源―欧州はギリシア・ローマからまっすぐに生まれたのではない。世界システムの大変動後、遠隔地交易、ローマ帝国との対抗、民族移動などを経て誕生した、500年にわたるフランク国家。「自由なる民」の淵源から王朝断絶までをたどる初めての通史。本巻では、初代王にいたる波乱の歴史を描く。
目次
第1部 起源の地を求めて(大西洋世界の展開と青銅器時代後期システムの崩壊;北海・バルト海地方と東地中海文化の接触;ローマ人のエルベ川流域への進出計画;ゲルマン諸部族の再編へ)
第2部 フランク同盟の盛衰(侵略と土地占取の時代;帝国に奉仕するフランク人;フランク首長層の台頭と転落)
第3部 フン族の影のもとで(五世紀初頭の政治動向とガリア;西ローマ帝国・ヴァンダル族・フン族;メロヴィング朝の起源とキルデリクス一世)
著者等紹介
佐藤彰一[サトウショウイチ]
1945年生まれ。1978年早稲田大学文学研究科博士課程退学。名古屋大学文学研究科教授などを経て、名古屋大学名誉教授、日本学士院会員、フランス学士院会員、博士(文学)。著書『修道院と農民』(名古屋大学出版会、1997年、日本学士院賞)ほか(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MUNEKAZ
20
先史時代からクローヴィスの父・キルデリクスの治世まで。泰斗によるフランク人の通史ということで、あとがき通りに完結すれば、壮大なシリーズになると思うが、それだけに「先生死なないでくださいよ」という編集者の言葉が重い。そもそもフランク人という民族はなく、様々な民族を内包した「フランク同盟」であったことや、「サリー」・フランクは存在せず、ユリアヌスの勘違いが後世に広まっただけなど、この方面には明るくない自分には衝撃的なことが多い。また著者の関心から、バルト海地域を中心とした琥珀交易についても詳しい。2021/09/29
洋書好きな読書モンガー
13
“Sword of the War God” by Tim Hodkinson を読む為に5世紀の西ローマ、ブルグンド族、フン族(アッティラ)の記事を確認に読む。2025/10/08
スターライト
7
フランス、ドイツ、イタリアなどの母胎ともいえるフランク王国。その400年に及ぶ歴史を詳述する画期的な書。本書では同王国成立までの前史を青銅器時代後期から説き起こし、文献に現れるまでの歴史は主として琥珀を手掛かりに民族の交流を叙述し、その後は残された文献や遺跡で跡付けながら各民族の消長を浮き彫りにする。ローマ帝国の皇帝や高官に似たような名前が出てきて判別が困難になるが、敵味方が交錯する様子はダイナミック。ただ、章ごとに地図や工程などの有力者の家系図などの図版ももう少し欲しかった。2021/10/30
スプリント
5
主要人物の名前に馴染みがなく同名の人物もいて じっくりと腰を据えて集中して読まないと時代の前後が繋がらなくなる。でも読んでいて楽しい。2024/04/21
ポルターガイスト
3
日本ではどマイナーなフランク史を3巻の大ボリュームで描く本邦初の概説書。初学者向けの概説となっているものの聞き馴染みのない人名が大量に出てきて読み飛ばしてしまう。ただまあこの分野の本を読めているというだけでも意義があるのかなと思う。あくまで高校世界史レベルでの知識落穂拾いに徹してしまったが,ブリテン島のスズや北欧の琥珀をめぐる交易網と国際商業語としてのケルト語というネットワーク史の視点が出てくると俄然面白い。ゲルマン人がローマ帝国に食い込みまくってる記述も多くイメージわいた。2025/09/14
-

- DVD
- メタル・ブレイド
-
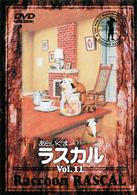
- DVD
- あらいぐまラスカル(11)






