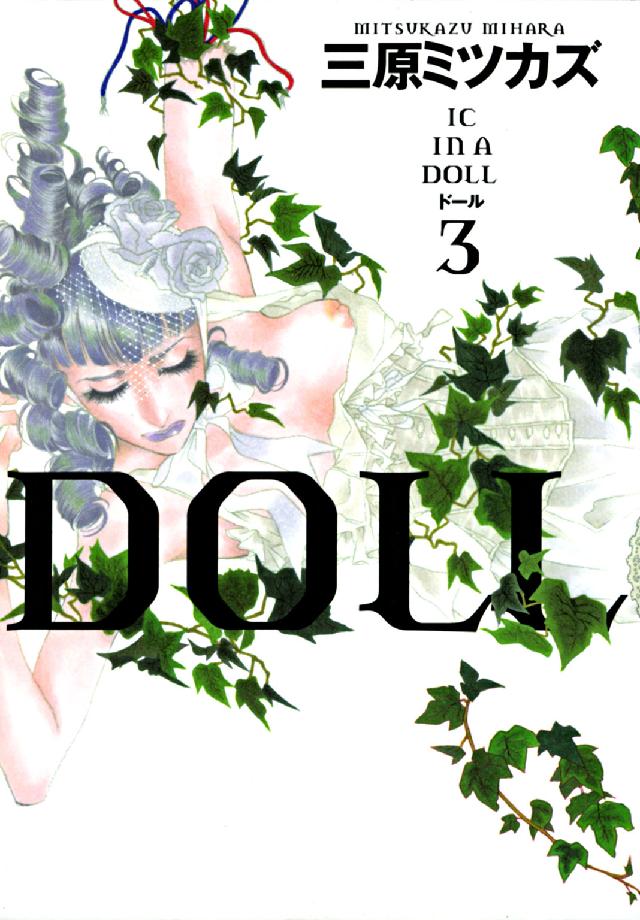内容説明
新幹線から防衛まで。戦後日本の復興と発展に、海軍技術者たちが果たした役割とは何か。造船、自動車、新幹線開発、土木などで高度成長を下支えした技術継受の全体像を復元、防衛生産も視野にその質的・量的インパクトを客観的に叙述するとともに、技術者たちの敗戦経験の歴史的特質をも浮き彫りにする。
目次
序章 海軍技術者とは誰か
第1章 造船王国の担い手へ―元海軍造船技術者の戦後
第2章 輸送機械・産業機械・電機へ―元海軍技術科(造機)士官の戦後
第3章 土木国家の源流―元海軍施設系技術者の戦後
第4章 流転する海軍将校―海軍機関学校卒業生の戦後
第5章 エリート技術者たちの悔恨と自覚―国有鉄道転入技術者・引き揚げ技術者の戦後
第6章 戦後防衛政策への展開―海空技術懇談会の設立とその活動
終章 軍民転換の歴史的特質
著者等紹介
沢井実[サワイミノル]
1953年生。1978年国際基督教大学教養学部卒業。1983年東京大学大学院経済学研究科第二種博士課程単位取得退学。現在、南山大学経営学部教授、大阪大学名誉教授、博士(経済学)。主著:『近代日本の研究開発体制』(名古屋大学出版会、2012年、日経・経済図書文化賞、企業家研究フォーラム賞受賞)ほか(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゲオルギオ・ハーン
24
軍から民間企業へのスピンオフについて大日本帝国の海軍技術者を事例として調べた一冊。スピンオフにより民間の技術力が底上げされ、経済成長に寄与するというのが一般的な考えだが、著者は「それは当たり前なのか」「技術者たちはそんな単純に割り切れたのか」という疑問を提示している。技術力を上げたのは間違いないが戦前から技術者を抱えていた三菱や川崎重工は元海軍技術者を敢えて採用していない。躍進を狙う日本鋼管や石川島重工業などの野心的な企業が採用していった。ベテラン技術者の中には技術メンターへの道を進んでいく方もいた。2025/02/09
無重力蜜柑
8
大日本帝国の海軍技術者(技術士官、技師、技手)が戦後に辿った経歴や発言の記録をもとに、彼らが戦後日本の高度経済成長や再軍備に果たした役割を描く。大量の史資料を渉猟、整理した超労作。名簿などに記録の残っている個々の技術者の経歴や発言を並列し続け、最後に総括を少し載せるという緻密な実証的構成になっているが、緻密すぎて少し眠い。資料的価値はある。戦後の海軍技術者の動向を左右したのは帝国海軍消滅と公職追放で、個人的・組織的ネットワークを通じてその動乱を生き延びた彼らの様子がよく見える。2022/08/21
Mealla0v0
5
戦前・戦中に動員された軍事技術者は戦後民間部門に散っていくが、その過程と海軍経験の意義を示す堅実な実証研究。技術者の再就職先に、他省への移転、新興企業など民間部門への就職が挙げられているが、民間では海軍で培ったネットワークが機能していたようだ。また、海軍技術者たちは「技術的後進性の痛切な自覚と後進性からの脱却こそ生き残った者の使命とする意識」=技術ナショナリズムを共有していたという。個人的には、技術者たちが、労働運動の激化が復興事業の妨げになることを懸念して第二組合を結成し労働運動を分断した点が興味深い。2022/12/01
-

- 電子書籍
- 古書店ロマンス【タテヨミ】第19話 p…