内容説明
大国が後退するとき―平和を維持する仕組みはいかに構想され、なぜ脆弱化したのか?国際連盟を含む複数の安全保障観やヨーロッパ派と帝国派のせめぎ合い等のなか、西欧への関与の揺らぐイギリスの外交姿勢と諸国との交渉過程を、膨大な史料から精緻に描き出し、現在への示唆に富む気鋭による力作。
目次
序章
第1章 西欧に関する戦後構想 一九一六~一八年
第2章 パリ講和会議における西欧安全保障問題 一九一九年
第3章 フランスとベルギーへの保障の再検討 一九一九~二〇年
第4章 英仏・英白同盟交渉の挫折 一九二一~二三年
第5章 ロカルノ条約の形成 一九二四~二五年
終章
著者等紹介
大久保明[オオクボアキラ]
1985年オランダ・ハーグ市生まれ。2008年慶應義塾大学法学部政治学科卒業。2009年ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)国際関係史修士課程修了。2016年慶應義塾大学大学院法学研究科政治学専攻後期博士課程単位取得退学。2017年同大学院より博士(法学)を取得。現在、日本大学国際関係学部助教(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
BLACK無糖好き
19
戦間期ヨーロッパ秩序が不安定なものとなった主たる原因を、ヴェルサイユ条約の内在的欠陥に求めるものは少なくないが、近年の研究では、国際連盟の機構を通じて条約の不備を平和的に解消する道筋も用意されていたと説いているようだ。本書はヴェルサイユ体制が安定的に運用されるための重要なアクターであるイギリスのとった外交政策、とりわけ西欧安全保障政策に注目し、その推移を一次史料に基づいて分析し叙述している。欧州安定へのコミットと大陸との距離感、英国の揺れ動く内実。◇『ミュンヘン会談への道』を読む前に本書を読みたかった。2018/11/12
hurosinki
6
1916年から1925年までのイギリスの西欧安全保障政策を、大陸関与という視点から膨大な一次資料に基づき実証する。終章で議論を要約してあるので先にそっち読むのが良いかも。 戦後秩序構想は16年から既にイギリス政府内で検討されており、外務省は英仏白で同盟を結ぶことを提案していた。しかし18年には同盟構想は下火になり、代わって連盟による安保体制の確立を目標とした。2021/01/11
ワッキー提督
2
第一次世界大戦中の戦後構想から、政策的・外交的な変遷にさらされつつ、最終的にロカルノ条約として結実する、戦間期西ヨーロッパの国際秩序について、イギリスの視点から追った一冊。 この分野にそこまで詳しくなかったが、丁寧な論述により少しは理解できたように感じた。2021/05/09
わび
2
大戦中の戦後秩序案からロカルノ条約で一先ずの解決を見るまで、およそ十年間のイギリスの対西欧安全保障構想を扱った研究。条約は結ばれたものの、アメリカが体制を去り、イギリス自身も孤立に戻ろうとする中で、自身の負担を増やさずにいかに西欧を安定化させるかというイギリス外交の格闘は、ヴェルサイユ条約の懲罰的側面を第二次大戦の原因に直結させるような議論へのカウンターとなるだろう。また、地域的な安全保障体制や同盟と、国際連盟の集団安全保障体制のどちらを重視するかという議論もその後を考える上で重要であるように思われる。2019/06/07
バルジ
2
1916年から1925年のロカルノ条約調印までのイギリスが志向した西欧安全保障政策を描く一冊。 膨大な史料から一つ一つ細やかに事実を紡ぐ一方、ヨーロッパ大陸への「関与」と「離脱」のせめぎ合いが本書の軸となる。「公平な調停者」として慎重に大陸へのコミットメントを検討するイギリス外交の姿は現在のブレグジッドを巡る混乱からは想像つかないものがある。また本書内で重要な役回りを演ずることとなる「帝国派」として欧州への関与政策を批判したカーゾンやスマッツといった人物の思想的背景も気になるところである。2019/04/14
-

- 電子書籍
- Love or Money?【タテヨミ…
-

- 電子書籍
- 復讐のラ・モール~お前たちには、地獄す…
-

- 電子書籍
- 【単話版】白豚貴族ですが前世の記憶が生…
-

- 電子書籍
- 東の空に沈む【単話版】 第11話~その…
-
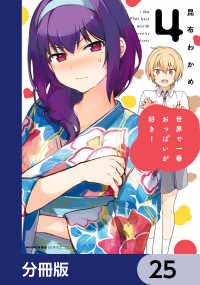
- 電子書籍
- 世界で一番おっぱいが好き!【分冊版】 …




