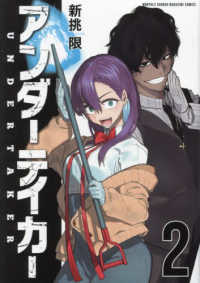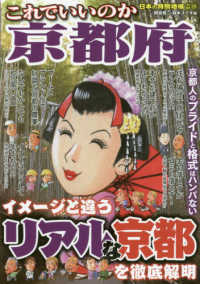目次
1 ロボットから倫理を考える(機械の中の道徳―道徳的であるとはそもそもどういうことかを考える;葛藤するロボット―倫理学の主要な立場について考える;私のせいではない、ロボットのせいだ―道徳的行為者性と責任について考える;この映画の撮影で虐待されたロボットはいません―道徳的被行為者性について考える)
2 ロボットの倫理を考える(AIと誠―ソーシャル・ロボットについて考える;壁にマイクあり障子にカメラあり―ロボット社会のプライバシー問題について考える;良いも悪いもリモコン次第?―兵器としてのロボットについて考える;はたらくロボット―近未来の労働のあり方について考える)
著者等紹介
久木田水生[クキタミナオ]
1973年生まれ。2002年京都大学大学院文学研究科博士後期課程研究指導認定退学。2005年京都大学より博士(文学)を取得。現在、名古屋大学大学院情報科学研究科准教授
神崎宣次[カンザキノブツグ]
1972年生まれ。2004年京都大学大学院文学研究科博士後期課程研究指導認定退学。2008年京都大学より博士(文学)を取得。現在、南山大学外国語学部教授
佐々木拓[ササキタク]
1976年生まれ。2004年京都大学大学院文学研究科博士後期課程研究指導認定退学。2008年京都大学より博士(文学)を取得。現在、金沢大学人間社会研究域人間科学系准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
27
ロボット・人工知能が我々にこれから問うことになるであろう数々の問題に対し、結局何が問題になるのか、何を対話していけばいいのかを倫理学で議論されてきたことをもとにわかりやすく論じてくれる。倫理学、これまで縁はなく論者の名前や学説もほぼ知らなかったが、こんなに有効なものだったのかと思い知る。◇ロボットといっても、アトムのような自律性の高い存在とガンダムのような人間拡張ツールどちらを想起するかで大きく違う。基礎教養(笑)いっぱい持ってる僕らは、この議論かなり有利かもな。◇asifの議論は対GAFAに不可欠かも。2019/08/16
izw
11
倫理とは何かを押さえた後、ロボットが道徳的行為者となれるか責任を持たせることはできるか、道徳的被行為者となれるか、プライバシーの問題、ロボット兵器の問題など、倫理学に関する論点を簡潔にまとめている。これから読むべき書籍の紹介も丁寧で、人工知能・ロボットと人間の関わりを考えていくための最初の一冊としては非常によい。2017/07/17
ソーシャ
6
ロボット倫理学の諸問題を通じて、関係する倫理学の議論を紹介した入門書。ロボットの登場によりどのような倫理的問題が生じうるのか、その問題について倫理学はどのようにアプローチしうるのかが平明に解説されています。責任主体についての議論やプライバシー、人工知能、無人兵器などロボット倫理ならではのテーマがたくさん扱われていて、通常の倫理学のテキストとは一味違った倫理学入門になっているので、ある程度倫理学を学んだことがある人にとっても得られるものが多い本だと思います。2017/03/30
かおる
3
倫理学ペーペーのわたしでも、ロボット工学からの斬新な切り口から入口へ入れた本です。特に興味深かったのは軍需における自律型兵器と、少子高齢化社会には欠かせないであろう介護ロボットの在り方。実用化もそう遠い未来では無い。余談ですが、いちおうアートや創作を生業としている身には、人工知能には絶対に負けたくないなあ…と思いました。2018/01/26
Myrmidon
3
ロボットや人工知能に関係する倫理学説や倫理学的問題を幅広く解説する。自分にはやや入門的過ぎる印象もあったが、理由反応性の話とか勉強になった内容もあり。ただ、自分は功利主義&概念道具主義的思考が好きなので、「自由や責任とは何か」よりも、「自由や責任をどう定義する方が使いやすいか(最大多数の幸福・選好充足に有効か)」を考えたいな。そーなると、やっぱり誰を功利主義的考慮の対象にするかという、ピーター・シンガー的問題圏(道徳的被行為者性)が本丸になるのか。2017/07/06
-
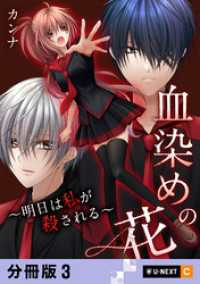
- 電子書籍
- 血染めの花~明日は私が殺される~ 【分…