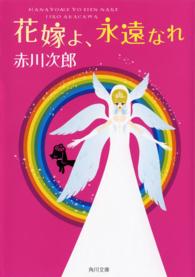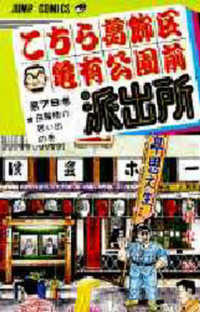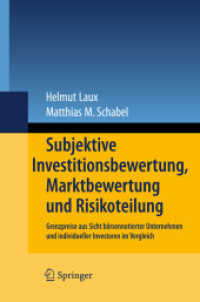内容説明
欧州発のアジア連合脅威論は、西海岸に押し寄せる移民への視線と結びつき、アメリカを「黄禍」の不安に陥れた。ジャーナリズムを介して増幅していく人種主義的言説は、鏡像たるアジア主義と作用し合い、日米関係にいかなる影響を及ぼしたのか。
目次
序章
第1章 日清戦争と日露戦争―日本脅威論の形成
第2章 第一次世界大戦とパリ講和会議―人種差別撤廃案の挫折
第3章 排日移民法と全亜細亜民族会議―黄禍論とアジア主義の鏡像関係
第4章 満洲事変から盧溝橋事件前夜まで―盛り上がるアジア主義運動
第5章 日中戦争という矛盾―日本の対外政策へのアジア主義の侵入
第6章 真珠湾攻撃の衝撃―米国の戦争政策への人種主義の関与
終章
著者等紹介
廣部泉[ヒロベイズミ]
1965年福井県に生まれる。1989年東京大学教養学部卒業。1995年ハーバード大学大学院博士課程修了。名古屋大学大学院環境学研究科助教授などを経て、明治大学政治経済学部教授、Ph.D.(歴史学、ハーバード大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
BLACK無糖好き
13
戦前・戦中アメリカ国内で黄禍論がどのように湧き上がったか、又、日本がアジア主義を唱えた事で、黄禍論がどのように極大化したかを、メディア等の記述から分析しアメリカの政策決定に与えた影響を探る。◆アメリカは戦後築き上げた国際秩序を、人種の枠組みで壊される事を避けたい意識が根底にあるのだろうか?。鳩山由紀夫が2009年に唱えた他愛もない"アジア共同体"論に強い拒否反応を示したり、最近のケント・ギルバートの著作もしかり。アジアでの国益確保の裏に人種対立(白色人種・黄色人種)に神経質な面があるのか気になる。2017/07/09
かんがく
11
黄禍論とアジア主義というコインの裏表。日中戦争期に入っても、欧米が日中の提携という「黄禍」を警戒していたという点は面白い。「半アジア」のソ連なども含め、「人種」問題は黒人やユダヤ人だけではない。タブー化せずに研究を深める必要がある。2020/08/24
バルジ
2
20世紀への転換期から主にアメリカでの「黄禍論」について地方メディアの論説など細かなものについても言及しているのが特徴だと思う。 黄禍論とアジア主義の相互作用の動きは読んでいて辛いものがあるが、当時の日本人の抱いて欧米に対する屈折した感情は理解できる部分が多々あることに気づいた。筆者は「人種戦争」という観点を戦争政策決定の視点から否定しているが、やはりそれ以外の市井の人々の人種観も大きく戦争に影響しているのではないだろうか。2017/12/14
Kazuo
1
日清戦争から日米開戦までの日米関係を調査している。その後に続く米国の占領政策の視点から記述しているように思う。考察はない。従って、著者が人種戦争という寓話からどんな教訓を得たのかが不明である。2017/12/11
てれまこし
0
黄禍論とアジア主義は表裏一体の思想。前者に触発された後者が生まれ、またそれが前者を増幅させていくというグローバルな思想史の一端が描かれている。結論は妙に卑屈であったが、その意義は個別の思想体系や国別の思想史では漏れてしまいがちな思想の往来を捉えたところにある。なぜ、もう少し早くこのような研究が行われなかったのか不思議になるが、これだけ複数の国々の史料を読み込みつなげていくことになると、高い語学力を備えた人が相当の手間暇をかけて調査しないとならない。現状の研究者育成では、なかなか手が付けにくい話ではある。2018/04/05