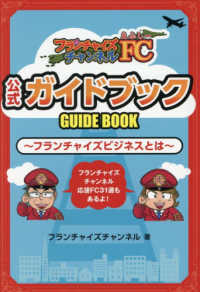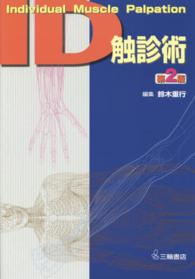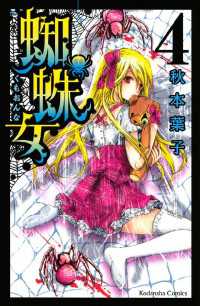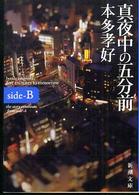内容説明
「我らの大学」はいかに始まったか。終戦後の混乱の中、200校以上が慌ただしく発足した新制大学。それは実に大転換だった。文部省やGHQ、諸学校関係者が議論・交渉し、戦前以来の改革構想やアメリカ式の高等教育モデルの間で揺れながら出発に漕ぎつけた困難な過程をたどり、日本のマス高等教育の原点を明らかにする。
目次
プロローグ
第1部 戦時体制と高等教育(戦時下の高等教育改革;高等教育の決戦体制)
第2部 戦後の高等教育改革(使節団報告書から学校教育法へ;学校教育法以後)
著者等紹介
天野郁夫[アマノイクオ]
1936年神奈川県生まれ。一橋大学経済学部・東京大学教育学部卒業。東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学。名古屋大学教育学部助教授、東京大学教育学部教授、国立大学財務・経営センター研究部教授などを経て、東京大学名誉教授、教育学博士。著書『試験の社会史』(東京大学出版会、1983年、サントリー学芸賞受賞;増補版、平凡社ライブラリー、2007年)他多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Ucchy
0
前半は日中戦争から敗戦までの高等教育改革について。戦争遂行のため、科学技術が重視され理系が大拡充されその遺産は戦後にも引き継がれた。後半は占領期の教育刷新委員会における新制教育制度の制度設計。現在まで続く学校制度、教育制度の根底が決まる。教刷委の迷走、タイムスケジュールに終われて玉虫色の結論を出す、外国の制度を詳しく知らないまま参考にするのは今と同じだなと思う。六三三四制、修士号の創設など主要なフレームワークはGHQの示唆によるもので外圧があって初めて大改革は実現するのかなと思った。2017/05/04