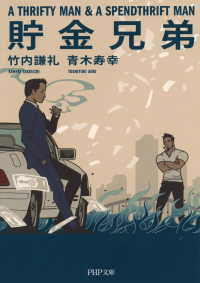内容説明
シベリアから「満洲」へ。露・中・日・仏・米が角逐する国際政治の焦点。海運とも連動する鉄道事業経営と、収用地や警備隊による植民地経営が一体となった「植民地化会社」の全貌を初めて解明。新しい跨境的な東北アジア近現代史を描きだす。
目次
序章
第1章 中東鉄道をめぐる国際環境
第2章 中東鉄道の組織構造と社員
第3章 鉄道事業―路線、収支、貨客の分析
第4章 鉄道・港・海運の「三位一体の交通システム」
第5章 植民地としての収用地の形成と変容
第6章 燃料資源の確保をめぐる苦闘
第7章 中東鉄道警備隊と護路軍
終章 「植民地化会社」の「罪と罰」
著者等紹介
麻田雅文[アサダマサフミ]
1980年生。2003年学習院大学文学部史学科卒業。2010年北海道大学人文科学研究科歴史地域文化論スラブ社会文化論専修博士課程単位取得後退学。2011年北海道大学より博士(学術)学位取得。日本学術振興会特別研究員(PD)を経て現在、ジョージ・ワシントン大学エリオット・スクール客員研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
BLACK無糖好き
20
ロシア帝国がシベリア鉄道の短絡線として中国東北へ展開した中東鉄道の経営の変遷。関係各国の経営の主導権争いとそれに伴う軍事的緊張が常に内在していた。特に本書はロシア/ソ連側の内部事情を詳らかにしている点が特徴。同鉄道は、中国東北をロシア極東にとっての緩衝地帯とする地政学的な役割と、ロシアと中国間の貿易進展の役割があった。又、ロシア革命後、中国東北が反革命派の牙城であったこともソ連が経営に参画し続けようとした一つの要因。◆満洲国に関連する本を読む前に本書を読んでおくべきだった。この地域への理解を深められる。2020/09/14
トクナガ
5
満鉄について書いてある本はよくあるけど中東鉄道についての本はあまりないので知らない話が多く面白かった。特に露清銀行と清朝の間で結ばれた敷設契約第6項の話は興味を惹いた。収容地という概念が面白い。やっぱり土地権利関係(領土含め)は面白いと思う。2024/10/10
竜王五代の人
5
国家の手先となって特定地域の植民地化を図る会社として、鉄道会社の中では最右翼たる中東鉄道の経営を分析する本。結局、苦労苦心の末、ロシア(ソ連)も現場の中国・満州も、日本もみんな不幸になったというオチ(植民地なんてそんなものかもしれない)。バッファーゾーンが欲しいなんて簡単に言うな。2024/09/20
相馬
2
新年読了1作目。中東鉄道(東支、東清鉄道)そのものについて、主にロシアからの視点で概観した良書。何故中東鉄道が建設され、どういう役割を担ったか、それを露清交渉やロシア内部の異見を詳細に拾っていて興味深い。更に当然当時の国際関係が中心になるが、それだけでなく、中東鉄道そのもの、組織や社員、経営収支、輸送貨物、燃料資源まで調べていて実に面白い。日本や満鉄から見た、当時の北満州情勢は目にするが、中東鉄道そのものをここまで詳細に研究した書は唯一といって良いのではないだろうか。面白かった。2015/01/01
どうろじ
0
ロシア人の考えは壮大にすぎてよくわからない。2018/11/28