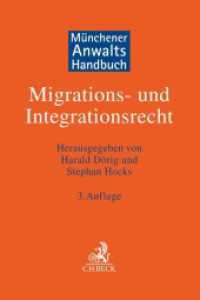出版社内容情報
2008年日本公共政策学会賞著作賞受賞
内容説明
比較政治制度論からのアプローチにより、戦後の議会と首長の個別公選制下における地方政府の政策選択の大きな変化を実証、大規模なデータ分析と事例分析をもとに、知られざる地方政府の政治的ダイナミクスをかつてない水準で描き出す。地方政治論に新たなフロンティアを拓く画期的論考。
目次
序章 課題としての地方政治
第1章 地方政府の比較政治学―理論的検討とモデル
第2章 戦後日本の知事と議会―独立変数の基礎データ
第3章 財政と政策の長期的変化―従属変数の基礎データ
第4章 革新自治体隆盛期の政策変化―一九六〇年代‐七〇年代前半
第5章 保守回帰期の政策変化―一九七〇年代後半‐八〇年代
第6章 無党派知事期の政策変化―一九九〇年代以降
終章 結論と展望
著者等紹介
曽我謙悟[ソガケンゴ]
1971年生まれ。1994年東京大学法学部卒業。東京大学大学院法学政治学研究科助手などを経て、大阪大学大学院法学研究科准教授
待鳥聡史[マチドリサトシ]
1971年生まれ。1996年京都大学大学院法学研究科博士課程中退。大阪大学大学院法学研究科助教授などを経て、京都大学大学院法学研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Ryueno
3
比較政治制度論を用いて日本の地方政府の政策選択を分析した本。「日本の地方政治の制度的な特徴は、首長と議会の間に非常に幅広い関係を成立させうる点にあ」ることから(p.49)、制度のみでは帰結が一意的な解とならない。そこで、比較政治制度論に中央地方関係や住民の政策選好などの文脈的要因を取り込んで、「地方政治要因の文脈依存的効果論」というモデルを構築したところに本書の面白さがある。文脈的要因を織り込むことで、知事と議会の選好が明らかになるとともに、両部門の選好が政策選択を規定するというのが本書の結論となる。2015/02/03
メルセ・ひすい
1
9-51 赤57 二つの民意=首長と議会 地方政治の機能を解析する。 第一次地方分権や三位一体改革の結果、地方自治体の財政状況に大きな格差が生じるようになり、あらためて知事や地方議会の重要性と責任が問われるようになってきた。とくに、財政については地域特性など他の要因も含めて自治体のよりよい予算の執行について分析が必要である。比較政治制度論からのアプローチにより、戦後の議会と首長の個別公選制下における地方政府の政策選択の大きな変化を実証。なお、この分析は大規模なデータ分析と事例分析を根拠としている。2008/03/09
Ekai Sunahara
0
ゼミに入っていた2人の先生の共著。地方政治は、制度が均一的なため、比較政治学の研究対象として、非常に優れていることが強調されていた。しかし、これまで十分に実証研究されてこなかった。おそらく、これから論文が増えてくる分野であろう。 本書の内容はというと、首長と議会に着目し、時代ごとに両アクターが、政策形成にどのような影響を与えて来たかを、定量分析、定性分析の両面から明らかにしている。 まだまだ解明されていない事柄も多いので、これからも地方政治に関する政治学には注目していきたい。2017/03/20
きやてい
0
重ッ2012/12/10