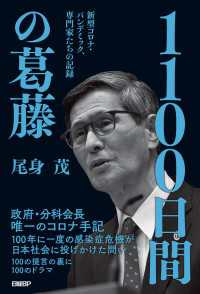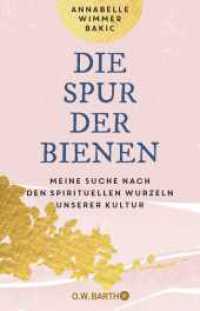出版社内容情報
本を読む人の頭の中で、一体何が起きている?
読書だけが私たちの脳にもたらす能力を科学的に解き明かす。
▼本書で解説している、読書と脳についての謎
・なぜ「紙の本」で読んだ内容は記憶に残りやすい?
・読書によって「頭が良くなる」のはなぜ?
・漢字と仮名が混ざった文章を、脳はどうやって理解している?
・読書中に、内容と関係のないことを考えてしまうのはなぜ?
・「快読」「精読」「音読」の科学的な使い分けとは?
・読書のモチベーションを上げる科学的な方法とは? など多数。
情報過多とデジタル化の波によって、脳は常に疲弊しています。
本書は、そんな時代に読書だけが私たちにもたらすものを、脳科学の視点から解説します。
読書好きの方、読書の持つ科学的な力を知りたい方は必読の一冊。
【目次】
目次(仮)
はじめに あなたの脳は読書で変わる
第1章 読書の今をひも解く――データで見る「読まない時代」の現実
読書をしない子どもたち/子ども時代の読書体験が人生を変える?/犯人はスマホ? 減り続ける「紙の読書」/「文字離れ」ではなく「読書スタイルの変化」/読書量の減少は「冊数」だけでは測れない/情報の洪水から身を守るための「紙の本」の力/「脳内マップ」が記憶を助ける/実験で分かったスマホ読書の「不都合な真実」/難しい本ほど「紙」で読むべし/「スキャン読み」の落とし穴
第2章 読書がもたらす脳科学的メリット
脳が新しい刺激を求めてしまう理由/なぜ、脳はすぐに疲れてしまうのか?/ヒューリスティックが引き起こす「認知バイアス」の問題/メンタル不調をもたらす「反芻思考」の謎/読書が脳の「休息」になるしくみ/読書中の「心のさまよい」は悪いこと?/読書がもたらす脳と身体のリラックス効果/読書で「頭がよくなる」脳科学的メカニズム/読書が認知症予防になる理由
第3章 文字と言語処理の脳メカニズム
書けないけど「読めちゃう」漢字の不思議/なぜ世界には二種類の文字があるのか?/表意文字(漢字)の脳内処理/表音文字(アルファベット、ひらがな、カタカナ)の脳内処理/日本語を読む脳は、驚くべき「二刀流」の使い手/日本語が読めるのに読書しないなんてもったいない!/話し言葉としての日本語の力/日本語を聞くことが想像力のトレーニングになる/耳で聴く読書の可能性/字幕付き動画や映画は情報過多?/読書がもたらす「快感」の正体
第4章 認知バイアスとセルフトーク――自分を操る脳のしかけ
都合のいい情報ばかり集める脳のクセ/注意力を操って読書をもっと楽しく!/脳の数だけ「現実」がある?/知恵ブクロ記憶とは何者か/脳の作業台、「ワーキングメモリ」の役割/知識の「棚」を組み替えるスキーマの力/柔らかい脳を育てる「シナプス可塑性」/読書中のセルフトークに注目!/ネガティブセルフトークの影響/読書によって得られる「精神的自由」
第5章 脳が喜ぶ読書テクニックとアウトプット術
「快読」って何?――飛ばし読みの極意/「精読」って何?――脳メカニズムと活用法/「行間を読む」とはどういうことか/「音読」はなぜすごい?――脳の力を最大限活かす/なぜ「読みっぱなし」では記憶に残らないのか/読書習慣を身につける実践法/「クエスチョン立て」の実践/「読書カード」の活用術/その他の実践的Tips/「最強の読書法」をすでにあなたは経験している
第6章 読書がもたらす共感力と社会性
読書は「著者とのコミュニケーション」――ミラーニューロンの秘密/共感力が人類を進化させた/「精神的自由」を失ってはいないか/読書を通じて広がる「精神的自由」/未来への展望と創造性の涵養
あとがき
内容説明
読書は単なる情報収集ではなく、あなたの「脳」を創る行為。なぜ、紙の本で読んだ内容は記憶に残りやすいのか?なぜ、物語を読むと登場人物に感情移入できるのか?―その答えは、あなたの「脳」に隠されています。本書では、読書が私たちの思考力や想像力を高める驚きのメカニズムを、最新の脳科学をもとに解き明かします。押し寄せる情報の波に疲れがちな今だからこそ知りたい、読書の科学的な意味がわかる一冊。
目次
第1章 読書の今をひもとく―データで見る「読まない時代」の現実
第2章 読書がもたらす脳科学的メリット
第3章 文字と言語処理の脳メカニズム
第4章 認知バイアスとセルフトーク―自分を操る脳のしかけ
第5章 脳が喜ぶ読書術
第6章 読書がもたらす共感力と社会性
著者等紹介
毛内拡[モウナイヒロム]
お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系助教。1984年、北海道函館市生まれ。2008年、東京薬科大学生命科学部卒業。2013年、東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程修了。博士(理学)。日本学術振興会特別研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター研究員等を経て2018年より現職。同大にて生体組織機能学研究室を主宰。専門は、神経生理学、生物物理学。「脳が生きているとはどういうことか」をスローガンに、基礎研究と医学研究の橋渡しを担う研究を行っている。第37回講談社科学出版賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
購入済の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
kinkin
奈
ロクシェ
小太郎