出版社内容情報
チャンネル登録者数28万人の大人気金運上昇YouTuberによる、
龍神を味方につける金運法!
漫画とタスクで「何を」「いつ」やればいいのか丸わかり!
金運を上げたいと思う人にとって欠かせないのは、無理な節約でもなければ、リスクを顧みない投資でもありません。金運に関して話すときには必ず名前が出てくるといっても過言ではない、「龍神さま」なのです。
実は、日本では古くから金運や開運に「龍」が用いられてきました。そんな、とてつもないパワーを持っているとされる古くから人気の高い龍神ですが、ただ龍の置物などを家に飾れば金運がアップする、というわけではありません。では、どのようにして「龍神」を引き寄せて金運をアップしていけばいいのでしょうか?
そこで本書では、金運アップの具体的実践方法を発信し、高い支持を得ている金運師兼YouTuberのたかみーが、龍神の解説や金運との深い関係、龍神を味方につける方法や家づくり、実際に金運を上げる龍神を活用した行動リスト、龍に関係のある吉日や神社などを紹介します!
漫画で解説しているので、毎日忙殺されて時間のないあなたでも、サクッと読めてすぐに理解できる内容になっています。
これ一冊で、龍神を味方につけて金運が爆上がりするはず!
【目次】
第1章 金運アップには「龍神さま」が欠かせない!
日本は龍の国! なぜ「龍」は金運・開運に用いられるのか?
龍神さまは「願ってばかりで少しも行動しない人」が嫌い!
龍神さまは「ハッピーなエネルギー」を持とうと努力している人が大好き!
第2章 龍神さまを味方につける金運習慣
「ハッピーな努力」で、「がむしゃらな努力」とはさよならしよう
必ず毎日一歩を踏み出すために! 自分の「何かやる」タスクをつくろう
お金は囲っても意味がない! ハッピーなエネルギーの流れを意識しよう
朝晩の習慣化で金運を引き寄せる! 龍神さまと繋がるための「おしゃべり」方法
第3章 龍神さまが住んでくれる!「金運家づくり」
龍を呼ぶにはどうする? 龍神さまに好かれる「家づくり」のポイント
何はともあれ玄関を! 玄関を入って「東側」が龍神さまの居場所
人も龍神さまも必ず通る「廊下」の整え方
龍神さまもお風呂が大好き! お風呂での過ごし方
龍神さまの「滞在時間」も延ばせるリビングづくり
見落としがちな「窓」も龍神さまが気にするポイントだった!
龍神さまがエネルギーチャージする場所は○○だった!
最終的には龍神さまが住む「養龍」の家へ!
第4章 的確タスクで龍神さまを逃さない!「龍神の大吉日」にすることリスト365
一生使えるタスクで龍神さまを引き寄せる!「龍の大吉日」と「することリスト」
「龍の大吉日」には、龍神さまとご縁のある神社に行こう!
龍の大吉日カレンダー
内容説明
金運を上げるのは、いつもあなたの「行動」次第です。でも、その行動が、継続が、難しい。そんなときに、きっと本書の「することリスト」と「大吉日カレンダー」が役に立つでしょうし、「龍神さま」があなたの金運をより一層上昇させてくれるでしょう。本書を手に取ってくださったあなたは、もうすでに金運アップのための大きな一歩を踏み出せているのですから。
目次
第1章 金運アップには「龍神さま」が欠かせない!(日本は龍の国!なぜ「龍」は金運・開運に用いられるのか?;龍神さまは「願ってばかりで少しも行動しない人」が嫌い! ほか)
第2章 龍神さまを味方につける金運習慣(「ハッピーな努力」で、「がむしゃらな努力」とはさよならしよう;必ず毎日一歩を踏み出すために!自分の「何かやる」タスクをつくろう ほか)
第3章 龍神さまが住んでくれる!「金運家づくり」(龍神さまを呼ぶにはどうする?龍神さまに好かれる「家づくり」のポイント;何はともあれ玄関を!玄関を入って「東側」が龍神さまの居場所 ほか)
第4章 的確タスクで龍神さまを逃さない!「龍神の大吉日」にすることリスト365(一生使えるタスクで龍神さまを引き寄せる!「龍神の大吉日」と「することリスト」;「龍神の大吉日」には、龍神さまとご縁のある神社に行こう! ほか)
著者等紹介
たかみー[タカミー]
金運上昇にまつわるさまざまなことを伝える金運師。YouTube『金運上昇チャンネル』を運営し、登録者数は28万人を突破。金融会社で3年6カ月連続営業成績1位を達成し、飲食店を開業するも人間関係で悩み、自殺未遂、引きこもりを経験した時代に1500万円の借金を抱える。「目先のお金を追う」から「お金を含め、他者のことを考える」ようにした結果、あとからお金が入ってくるようになり借金完済。以後、前を向けずに苦しんでいる方に寄り添い、1人でも多くの方が前向きに人生を踏み出せるようにと発信を続ける
こげのまさき[コゲノマサキ]
マンガ家、イラストレーター。育児レポートや解説マンガを得意とする。かゆいところに手が届く取材にも定評があり、マンガで誰にでもわかりやすく解説する技術は評判が高い(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 異世界建国記【分冊版】 86 角川コミ…
-

- 電子書籍
- 裏切られた妻たち【タテヨミ】第2話 H…
-
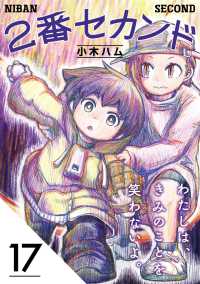
- 電子書籍
- 2番セカンド【分冊版】17
-
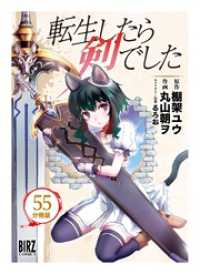
- 電子書籍
- 転生したら剣でした 【分冊版】 55 …
-
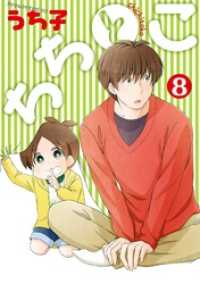
- 電子書籍
- ちちとこ 8巻【デジタル版限定特典付き…



