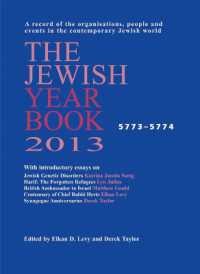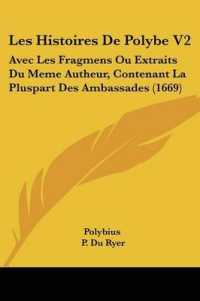出版社内容情報
自閉スペクトラム症、ADHD……
診断名よりも大切なこと
診断名はあくまでもその子の一部にしか過ぎません。「自閉スペクトラム症のAくん」「注意欠如・多動症(ADHD)のBちゃん」といった視点よりも、大切なのは、その子の目線にまで達して、気持ちを想像してみること。本書では、「発達障害」と診断される可能性のある子どもたち12のストーリーを例に、その子の気持ちを想像し、困っていることを探り、「仮の理解」を行う過程を解説。わが子の「不可解」な行動に、悩める親や支援者を応援する一冊です。
【内容】
この本は、わが子の育ちを心配する保護者の方に手に取ってもらえたらという思いで書きました。
発達障害について解説する本は、たくさんあります。
でも、漠然とした「不安」を抱えた保護者の方がまず初めに思うのは、わが子にどんな診断がつくのかということよりも(もちろん、それも大切なことではありますが)、ただただ毎日を穏やかに、楽しく、わが子の成長を喜びながら関わりたい。そのために、今ある「不安」を少しでも軽くしたいといったことではないでしょうか。
例えば、どうして夜に寝てくれないの? どうして外で困らせるの? どうして言うことを聞いてくれないの……?
そんなわが子に向かって最初に願うことは、「ただ、この子とうまくつき合いたいだけ。
この子が感じていること、思っていることを知りたいだけ」。
親は、「この子とうまく関わりたい」と、毎日毎日、思っていることでしょう。
"わかってしまったような気になってしまう"「発達障害」という名前だけでは、そんな思いにはじょうずに向き合えないように思います。
「発達障害」だけで子どもを見ないで、この本がそんなたくさんの「不安」をほんの少しでも軽くすることができればと願って、考えながら書きました。
――「はじめに」より
内容説明
自閉スペクトラム症、ADHD…診断名よりも大切なこと。診断名はあくまでもその子の一部にしか過ぎません。「自閉スペクトラム症のAくん」「注意欠如・多動症(ADHD)のBちゃん」といった視点よりも、大切なのは、その子の目線にまで達して、気持ちを想像してみること。本書では、「発達障害」と診断される可能性のある子どもたち12のストーリーを例に、その子の気持ちや困っている理由を想像し、「仮の理解」を行う過程を解説。子どもの「不可解」な行動に、悩める親や支援者を応援する一冊です。
目次
第1部 子どもの心と行動を理解したい!(乳児期(0~3歳ごろ)―1歳半ごろから心配が表面化
幼児期(3~6歳ごろ)―初めての集団生活への不安
就学期(6~7歳ごろ)―就学先選択という一大テーマ
学童期(6~12歳ごろ)―小学校生活の3つのステージ
思春期(12~17歳ごろ)―親との距離感が大事な時期)
第2部 医療の役割―「診断名」を超えてその子に近づく(発達の診立て;「診断」について)
著者等紹介
田中康雄[タナカヤスオ]
現在、「こころとそだちのクリニックむすびめ」院長。北海道大学名誉教授。児童精神科医師。臨床心理士。1958年栃木県生まれ。1983年に獨協医科大学医学部を卒業後、旭川医科大学精神科神経科、同病院外来医長、北海道大学大学院教育学研究院教授、附属子ども発達臨床研究センター教授などを経て現職。発達障害の特性をもつ子どもとその家族、関係者と、つながり合い、支え合い、認め合うことを大切にした治療・支援で多くの人から支持されている。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さおり
はるごん
shizuca
鳩羽
chietaro