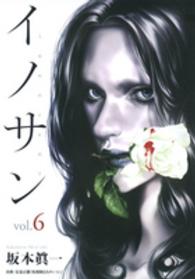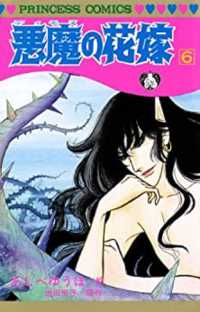内容説明
「新しい俳句が生まれなくては、俳句は滅ぶ。」無風の俳壇に、新しい風、新しい論を。
目次
宗田安正は、最後の一句で現代史を描く。[H25・2]
古沢太穂は、社会性俳句であり抒情俳句だ。[H25・7]
攝津幸彦と仁平勝とは、センチメンタルの共犯者だ。[H26・7]
星野高士が、戦後生まれ俳人の先頭に躍り出た。[H26・8]
宮崎大地句集の発見に、驚く。[H26・10]
兜太と汀子が、自分を語る。[H26・11]
震災俳句を五十嵐進は、どう読むか。[H27・3]
従軍俳句と軍事郵便で、民衆が手にしたものは。[H27・8]
新しい兜太を、岡崎万寿が浮かび上がらせる。[H27・10]
坪内稔典は、理論と実践を一致させる。[H28・3]
関悦史は、独自の活動をする。[H28・7]
中山奈々を読みつつ、明治・昭和・平成の俳句を考える。[H28・9]
楠本憲吉も鈴木明も、面白い。[H29・1]
平成の終わりに、アニミズムを考える。[H29・4]
現代俳句協会と、戦後俳句史とを振り返る。[H29・8]
「俳句」に先駆けて、「二十四節気」が無形文化遺産に。[H29・11]
兜太「海程」、狩行「狩」が終刊に。[H30・2]
兜太、逝く。[H30・5]
山下一海、復本一郎、堀切実は提言する。[H30・7]
高山れおなが、朝日俳壇選者に。[H30・8]〔ほか〕
著者等紹介
筑紫磐井[ツクシバンセイ]
1950年、東京都に生まれる。俳誌「沖」を経て、「豈」同人。現在、「豈」発行人。藤原書店「兜太Tota」編集長。評論集に、『飯田龍太の彼方へ』(深夜叢書社、1994年)[第9回俳人協会評論新人賞]ほか。詩論に、『定型詩学の原理―詩・歌・俳句はいかに生れたか』(ふらんす堂、2001年)[正岡子規国際俳句賞EIJS特別賞、加藤郁乎賞]、『伝統の探求〈題詠文学論〉』(ウエップ、2012年)[第27回俳人協会評論賞]ほか。現代俳句協会副会長 俳人協会評議員 日本伝統俳句協会会員 日本文藝家協会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
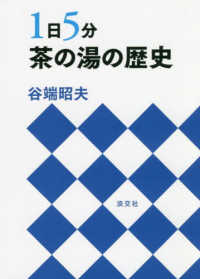
- 和書
- 1日5分茶の湯の歴史