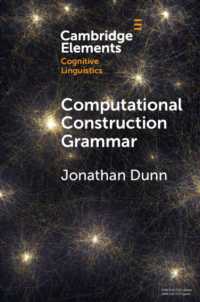内容説明
ホトトギス・馬醉木、そして新興俳句のめざましい抬頭による俳句群雄割拠の時代。俳壇史に残る不滅の名作!
目次
松本たかし句集(松本たかし)
白日(渡辺水巴)
白い夏野(高屋窓秋)
長子(中村草田男)
五百句(高浜虚子)
花影(原石鼎)
立子句集(星野立子)
海門(大野林火)
旗(西東三鬼)
草木塔(種田山頭火)
著者等紹介
松本たかし[マツモトタカシ]
明治39年1月5日、東京市神田に生まれる。本名・孝。44年、5歳で能の稽古を始める。大正8年、江戸期の文芸書や小説などを読み始め、芝居や寄席に通う。翌年、肺尖カタルに罹り、静岡で静養中に「ホトトギス」を読む。20歳頃、能役者の道を断念し、句作の機会を多く持つ。昭和4年、虚子選の巻頭。言葉に対する厳しさ、品格、美しさで「生来の文芸上の貴公子」(川端茅舎)といわれる。21年、「笛」創刊。31年5月11日没。享年50
渡辺水巴[ワタナベスイハ]
明治15年6月16日、東京市浅草区小島町に生まれる。33年、初めて読売新聞の角田竹冷選に投句。34年、内藤鳴雪に師事し、38年、千鳥吟社を結成。39年、「俳諧草紙」を創刊した。大正5年、「曲水」を創刊。昭和21年8月13日没。享年65
高屋窓秋[タカヤソウシュウ]
明治43年2月14日、名古屋市に生まれる。本名・正国。16歳の時、初めて句会に出席し、やがて秋桜子の俳句に魅かれて、「ホトトギスム」「馬醉木」に投句。法政大学英文科在学中にしばしば「馬醉木」発行所に出入りした。昭和5年、秋桜子に師事。口語表現による澄明なイメージを作風として、新興俳句の先進を担う。10年、「馬醉木」を去り、新興俳句誌「風」「広場」「京大俳句」に参加するが、13年、渡満、戦後、帰還して、「天狼」創刊同人となる。平成11年1月1日没。享年90
中村草田男[ナカムラクサタオ]
明治34年7月24日、中国福建省の日本領事館で生まれる。本名・清一郎。37年、母と帰国。松山中学、松山高校を経て、東大独文科に入学す。昭和4年、虚子を訪ね、東大俳句会に入会。8年、卒業後、成蹊学園で教鞭を執る。9年、「ホトトギス」同人。11年、第一句集『長子』を刊行し、写生に基づく新鮮な抒情の句風を確立した。14年、加藤楸邨、石田波郷らと共に人間探究派と呼ばれる。21年、「万緑」創刊主宰。58年8月5日没。享年79
高浜虚子[タカハマキョシ]
明治7年2月2日、松山市長町に生まれる。本名・清。九歳の時、祖母・峯が没したため、高浜の名跡を継いだ。伊予尋常中学で河東碧梧桐と同級になり、24年、碧梧桐を介して正岡子規を知る。25年、三高、27年、二高、しかし、中退して上京。漠然と小説家を志す。31年、「ホトトギス」を東京に移して、発行人となる。37年、漱石の「我輩は猫である」を「ホトトギス」に連載。自らも小説家を志し、「風流懺法」「斑鳩物語」「大内旅館」を発表した。44年、「ホトトギス」を純粋な俳句誌として再生を期した。虚子門からたくさんの優秀な俳人が輩出された。昭和34年4月8日没。享年85
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。