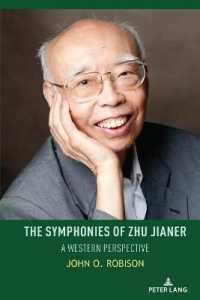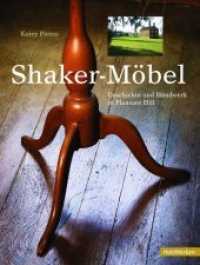内容説明
教育への問いは諸社会の歴史、人間のあり方そのものを問い直す旅につながる。本書は、映画やドキュメンタリー、ドラマ等の映像資料から、教育学の諸問題へ橋渡しをはかる入門書である。ジェンダーやマイノリティ、特別支援教育やいじめ問題など近年注目のテーマをカバーする。
目次
第1部 光の学校/カゲの学校(用務員室とスホムリンスキー(学習塾は本当に教育界の「日陰者」なのか)
分断とサンクチュアリ(出会うはずのなかった生徒どうしが集ったとき何が起こるか))
第2部 分ける教育/分けない教育(「七つの子」とユリの弁当箱(男女を別学/共学にする深いワケとは?)
分けない教育とヴァルネラビリティ(告白の主語はやはり「私」ではないか?)
救貧院と南北戦争(サリヴァン先生がなぜ「奇跡の人」になり得たのか))
第3部 社会としての学校/社会のなかの学校(疎開と福祉(子ども同士の世界にはなぜ暴力が充満するのか)
無償化と脱統制(教科書無償闘争はなぜ顧みられないのか)
綴方と世間(ありのままを書くことはなぜ大人に不都合を起こすのか))
第4部 良い生/悪い生/唯の生(夜尿症と揚げパン(なぜ私たちは「良き生」への執着を手放しがたいのか)
社会的オジと安保闘争(何も生産しないコペル君は何を与えているのか))
著者等紹介
倉石一郎[クライシイチロウ]
1970年兵庫県生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。東京外国語大学を経て、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。専門は教育学・教育社会学。短歌結社「心の花」会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。