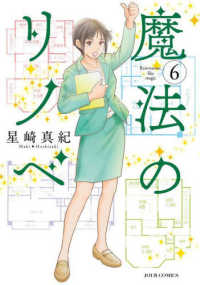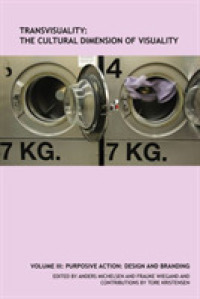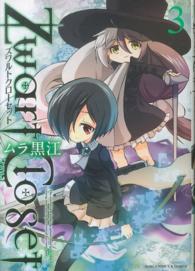目次
序章 資本主義的食料システムを考える
第1章 日本の近代的国家建設と製油産業の成立―19世紀~第一次世界大戦期
第2章 油脂産業の発展と油粕・植物油の用途拡大―世界大戦戦間期を中心に
第3章 米国産大豆による製油産業の再建―戦中~戦後再建期
第4章 食用油の需要拡大を促した構造―高度経済成長期を中心に
終章 資本主義による「食」の変容
著者等紹介
平賀緑[ヒラガミドリ]
1971年生まれ、広島県出身。1994年に国際基督教大学卒業後、香港中文大学へ留学。香港と日本において新聞社、金融機関、有機農業関連企業などに勤めながら、1997年からは手づくり企画「ジャーニー・トゥ・フォーエバー」共同代表として、食料・環境・開発問題に取り組む市民活動を企画運営した。2011年に大学院へ移り、ロンドン市立大学修士(食料栄養政策)、京都大学博士(経済学)を取得。植物油を中心に食料システムを政治経済学的アプローチから研究している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
人生ゴルディアス
9
大変面白かった。石油の政治経済学ならわかるけど植物油? と思ったが、大豆を主とする植物油にも、確かに政治と経済があったのだ……! 高度経済成長期に植物油の使用量が激増したのは、食の洋風化が原因とする定説に異を唱え、むしろ明治維新以降外貨節約のため殖産に努めた政府の後押しを受けた鈴木商店などの商社が、肥料としての大豆かすを満州に求め、大規模輸入に対応するため海港に作られた工場がほどなく軍事用油の生産にも乗り出したが、戦後は過剰な生産能力を持て余し、ついに加工食品に大口需要を見出していくという話。すごかった!2023/02/28
いぬたち
4
なんで俺こんな本買っちゃったんだろうって思ったけどなかなか面白かった。明治以降の食物油(主に大豆)の歴史という今まで聞いたことない題材だがそこがかえって新鮮で斬新なアプローチが取られていることが印象的だった。戦後は食の洋食化が進み油の需要が増えたとの定説があるようだが実は明治頃からの企業努力で徐々に進み概ね日本側の努力で油の需要を発展させてきたという著者の結論には感心せざるを得ない。2024/09/03
-
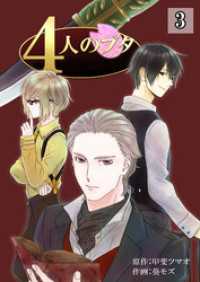
- 電子書籍
- 4人のブタ 3巻 コスモス