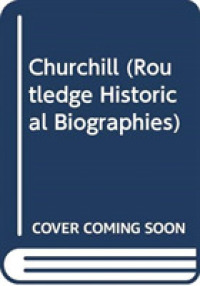目次
第1章 解体途上にある一〇〇〇の地域
第2章 多重化都市、テリトリアンの都市
第3章 俗都市化
第4章 俗都市化の四つの道程
第5章 「俗景観」、俗都市化の景観
終章 「俗都市化」に抗う
著者等紹介
ムニョス・ラミレス,フランセスク[ムニョスラミレス,フランセスク] [Munoz Ram´irez,Francesc]
バルセロナ自治大学地理学博士。現在、バルセロナ自治大学文学部で都市地理学・地域整備を教える傍ら、バルセロナ市歴史博物館との連携により、景観・遺産マネジメントの専門家・実務家を養成するマスターコースのディレクターを務める。バルセロナ自治大学の研究組織、戸建住宅地区観測院の所長を兼務。オランダ、イタリア、アルゼンチンをはじめとするヨーロッパ・中南米の大学で客員教員を務めた経歴をもち、現代都市論、都市計画、地域戦略などの分野で国際会議や展示会のディレクションを手がける
竹中克行[タケナカカツユキ]
地理学者、愛知県立大学教授。東京大学大学院総合文化研究科博士課程満期退学。博士(学術)
笹野益生[ササノマスオ]
京都大学工学部卒業、愛知県立大学大学院国際文化研究科博士前期課程修了。現在、愛知県立大学学術情報部勤務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いとう・しんご
5
「アフリカ潜在力」5巻に言及があり借りてみたら都市計画と都市景観(広義には地理学?)という未知の分野の本。’80年台以降のグローバル化と新自由主義によって都市計画が民間主導となった結果、都市の観光商品化が進んで、人々がスラムに追いやられたり、郊外の没個性的な住宅地に移り住んだりしていき、都市景観はbanal=通俗的でどれも同じようなものとなる一方、持続不可能な環境が広がった、というお話。世界各地の実例がてんこ盛りの中、モリカケの何倍もひどいロンドンとブエノスアイレスの話は一読の価値あり。 2022/01/21
ひつまぶし
1
ジェントリフィケーションが再開発と排除の構造的な把握だとすると、ムニョスの俗都市化という分析枠組みは、その具体的かつ個別の過程を読み解く手がかりとして、かなり使い勝手が良いように思える。場所の歴史や固有性にこじつけながら、結局はどこにでもあるようなイメージが埋め込まれていく。再開発の計画において、行政は私企業に公有地を払い下げるだけでなく、高値で売りさばくためのインフラ整備に多額の支出までしてしまう。理論的には状況証拠から最大公約数を導き出したような荒さも感じるが、逆に言えば分かりやすく、整合的でもある。2022/03/15
コウヘイ
1
難しい。 論旨としては、グローバル資本主義の発展に伴い、都市の公共空間が私有化され、結果的に都市景観が均質化して行くというもの。問題意識としてはすごく共感できるし、都市のパートタイム利用者の増加による都市空間の変容やイメージ先行の都市開発などは観光立国を進める日本の課題でもある。 ただやはり抽象的な議論が多く理解はおぼつかない。いずれにせよ、都心回帰による職住近接化がかつての混住スタイルとどう異なるのか、観光客の増加は都市をどう変えるかなど自分の問題関心を深めてくれる著作であったことは間違いない。2018/03/31