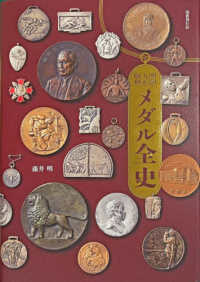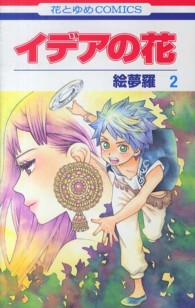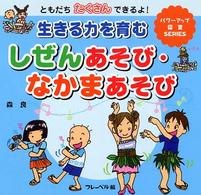目次
序章 ビザンツ帝国の存続―境界域の視点から
第1章 イサウリア人とビザンツ―帝国内「蛮族」の「ローマ化」と社会参加
第2章 北アフリカとビザンツ帝国
第3章 中期ビザンツ時代のケルソン―帝国北方外交の展開
第4章 ビザンツ領南イタリア―ビザンツ・西方・イスラムの衝突と交流の地
第5章 十一世紀初頭におけるアンティオキア・ドゥカトンの成立―ビザンツ帝国による北部シリア再征服とその統治
第6章 十一世紀後半のドナウ流域地方―ペチェネーグ人との共生空間
第7章 ノルマン戦争にみるビザンツ帝国の存続要件―中央政府と地域社会
第8章 一二〇四年とクレタ―外部勢力支配地域と中央政府の関係の変容
著者等紹介
井上浩一[イノウエコウイチ]
1947年生まれ。大阪市立大学名誉教授
根津由喜夫[ネズユキオ]
1961年生まれ。金沢大学人間社会研究域歴史言語文化学系教授(人文学類担当)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Toska
4
クリミアや北アフリカ、南イタリア、シリアなど、ビザンツ帝国の中でも「境界域」を中心に取り上げた論集。近代の国民国家とは異なる、多民族・多文化共存の可能性を秘めた帝国という、近年の帝国論に棹さした内容(序章参照)。とは言え、どの論文もビザンツの「多様性」を過剰に称賛するような味つけはされていないから安心して読める。寧ろ、多様性の中で帝国を保つ労力とコストの方が印象に残った。2022/12/15
MUNEKAZ
4
ビザンツ帝国の周縁部に焦点を当てた論集。一つ一つの論考は短く物足りない面もあるが、その代わり北アフリカやクリミア半島などといったビザンツ統治下についてあまり言及されることの少ない地域も取り扱っているのが嬉しい。「交流」と「共生」というよりは現地勢力との化かしあいといった印象も強いが、この内実の柔軟性がビザンツの強みでのあるのだろう。また地中海世界の大国としてビザンツ海軍が、地域内でかなりのプレゼンスを持っていたことが、いくつかの論から窺えて面白かった。2018/04/12
じょあん
1
ビザンツ帝国の周縁部についてとりあげる内容。コンスタンティノープル視点や西欧視点のビザンツを書いたものが多い中で貴重な一冊。各章とも対象とする地域の歴史についての良質な概説になっている。論文集の体裁をとるが難解な内容ではなく読みやすい。ひとつだけ残念なのは、アナトリア北東部が扱われていないこと。アルメニアやジョージア、また進出してきたセルジューク朝とも接触するなど重要な地域なだけにこの点だけは惜しまれる。2019/04/25
Teo
1
ビザンツ帝国の周辺部においてその外側の勢力との関係をテーマに持ち寄った論文の集成。特定の部分に注目している分、普段お目にかかれない様な論考があって面白い。2013/09/26
-

- 和書
- 初級職試験 長崎県版