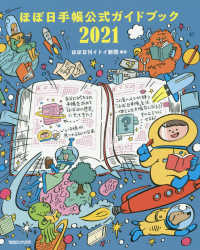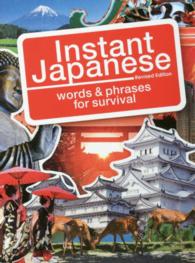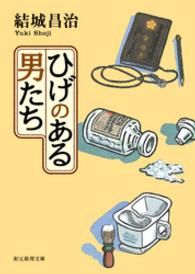内容説明
自分の悲しみや無力さを中心に地球が回っているという「精神の天動説」ではなく、自分自身が世界とともに動いていて、動く世界のなかに存在しているのだという「精神の地動説」に気づくために―。学生たちはアジアを歩き、東北の森に間伐に出かけ、マイノリティ(被差別少数者)をはじめとするさまざまな他者と教室で出会う。
目次
プロローグ 「精神の地動説」のほうへ
第1章 わたしの物語、他者の物語、「みんな」の物語(わたし自身の物語―少年期から青年期の「危機」をめぐって;「わたし」と他者の物語を分かちあう―大きな「みんなの物語」にあらがって)
第2章 見えない隣人としてのマイノリティ(教室のなかのマイノリティ―見えない隣人と出会う;当事者であることを選ぶということ―カミングアウトをめぐる往復書簡;人間の「差別」を考える10のテーマ―若者たちの挑発を受けて)
第3章 関係の貧困/孤絶の文化から「現場」体験へ(日本の子ども・若者の自己評価の低さについて―「関係の貧困」と「孤絶の文化」;学びへの誘いとしての「現場」体験―わたしの大学での実践から)
エピローグ 3・11後を生きる
著者等紹介
楠原彰[クスハラアキラ]
1938年、新潟県中蒲原郡の農村に生まれる。大学(新潟大学)・大学院(東京大学)で教育学を専攻。大学助手(東大)を経て、大学教員(専任國學院大學、多数の国公私立大学の兼任)として学生たちの学びと教育にかかわる。また、市民運動として反アパルトヘイト運動に参加してきた。90年代からはアジアやアフリカ諸地域を若者たちと歩く。現在、國學院大學名誉教授、日本ボランティア学会運営委員。「地下水」同人。大学で出会った若者たちと岩手県紫波町の里山の間伐作業に通い続ける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。