内容説明
食を新しい学問として開拓したパイオニアの四半世紀余にわたる論考を編む。既成の学問領域を超えた学際的・総合的食の研究成果。
目次
なぜ食の文化なのか
1 風土をみつめる(日本の風土と食卓―アジアのなかで;東アジアの食の文化;発酵の文化圏;東アジアの家族と食卓)
2 食文化の変化を追う(異文化と食のシステム;家庭の食卓風景一〇〇年;家庭料理の一〇〇年;飲みものの一〇〇年;昭和の食―食の革命期;都市化と食事文化;外食の文化史序説;食文化変容の文明論)
3 食の思想を考える(調理の社会史的考察;食における芸術性;食事作法と食事様式;食事における享楽と禁欲の思想;栄養の思想;食わず嫌い―悪食とタブー)
著者等紹介
石毛直道[イシゲナオミチ]
1937年生まれ。京都大学文学部卒業。農学博士。専門領域は民族学。国立民族学博物館教授、館長をへて、現在、国立民族学博物館名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
エリナ松岡
7
音楽で言うとベストアルバム的な位置付けで、過去の論文をまとめたものらしいです。どのくらい切り捨てられた部分があるのか不明ですが、かなりボリュームがあります。僕からすると、なんと言いますか、学術的なグルメ本のようでした。もちろん一般的なグルメ本とは掘り下げ方が違いますが決して難しいことはなく、グルメ本好きな方にはぜひ読んでもらいたいです。2018/12/29
とせ
0
日本、中国、朝鮮半島の食に関する年中行事一覧が、とても興味深い。中国起源の年中行事だからだが、中国では廃れたが日本なり朝鮮半島に残っている行事とあり、例えば正月のお屠蘇は現在の中国には全く残っていないんだそうな。塩辛の分布、日本文化における酒と茶の対立図がとくに好き。普段の食事が背景を知ることでより楽しくなる。2025/03/08
-
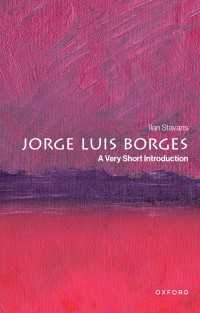
- 洋書電子書籍
-
VSIボルヘス
Jorge Lu…
-
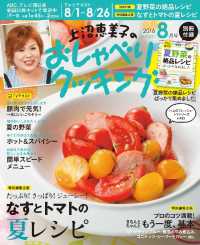
- 電子書籍
- 上沼恵美子のおしゃべりクッキング201…




