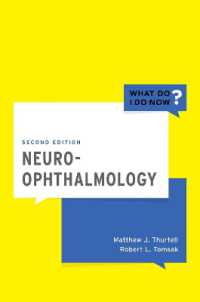出版社内容情報
子ども時代からシームレスに育てるプラスαの能力
●非認知能力の基盤は幼少期にあり!OECD2030 ラーニングコンパスに掲げられる「エージェンシー」を育てるためには、認知能力と非認知能力を、子ども時代からシームレスに育てることが重要です。
非認知能力の育成と、その発達に深く関わるアイデンティティと所属感の支援について、幼児から成人になるまでの育ちを見通していきます。
●成長してからでは、もう遅い?
非認知能力をスキルと捉えれば、幼少期を過ぎてからのリカバリーも十分に可能です。
安全行動の背景にある潜在的な不安をどう乗り越えさせるか、どんな足場かけがあればアクティブラーニングのような主体的な学びを成立させることができるか、リアルな学生の姿からタイプ別に解説します。
●Z世代とのギャップに悩む、管理職必見!
学生のタイプとリンクさせながら、いまの若手職員の特徴や、仕事への向き合い方、職場における内的適応や成長を促すコツを、解説します。
【目次】
はじめに
序 章 近年の大学生の姿から見えてくるもの――協働活動で浮かび上がる大学生のタイプ
第1節 近年の大学生の現状
1 教員からはどう見えているか?
2 企業からはどう見えているか?
第2節 協働学習を設定してわかったこと――大学生のタイプ 就職活動の成果との関連
1 協働活動への参加の仕方に見る学生の5つのタイプ
2 タイプごとの学生のイメージ
第1章 大学生のタイプと非認知能力との関連
第1節 資質・能力(コンピテンシー)とは――認知能力と非認知能力
1 非認知能力とは
2 自己に関する非認知能力
3 社会性・人とかかわる非認知能力
第2節 非認知能力と大学生たちの行動特性の関係
1 協働活動における大学生の各タイプと非認知能力の関係
2 大学生の非認知能力とこれからの教育
第2章 なぜ非認知能力の発達格差が生まれるのか――幼児期・学齢期の体験と非認知能力の関係
第1節 大学生が非認知能力を獲得するうえで不可欠な各段階での発達課題
1 乳児期(0歳~1歳半ごろ) 基本的信頼 vs. 基本的不信
2 幼児期前半(1歳半~3歳ごろ)自立性 vs. 恥・疑惑
3 幼児期後半(3歳~6歳ごろ) 積極性 vs. 罪悪感
4 児童期(6歳~12歳ごろ) 勤勉性 vs. 劣等感
第2節 心理的発達から見た大学生たちの行動特性
1 近年の大学生に見られる5つの傾向
2 青年期の発達課題になぜ向き合えないのか
3 安全行動をとり続けることの発達上のリスク
第3章 近年の大学生の支援のあり方
第1節 近年の大学生の対応は、自律性支援が基盤
1 大学生を支援することの難しさ
2 「安全行動タイプ」への支援の指針
第2節 「適応行動」への移行を促す支援のあり方
1 協働活動・学習への参加に、不安が高まらないようにする
2 不安ながらも、少しずつ適応行動をするように支援する
3 十分な足場かけをして、適応行動をさせていく
4 徐々に主体性や能動性を高め、自ら適応行動をするように支援する
第3節 学生のタイプに合わせた対応の工夫
1 気疲れさせるタイプにおける「行動化が弱いタイプ」への支援の指針
2 気疲れさせるタイプにおける「空回りするタイプ」への支援の指針
3 「リーダータイプ」への支援の指針
第4章 職場における自律性支援
第1節 近年の若手社員への自律性支援のあり方
第2節 上司・管理職に求められる対応
第3節 職場適応の問題
第5章 子ども時代に非認知能力を育てるには
第1節 幼児期
内容説明
「みんなと同じ」でいたがる若者たち。人と違う行動で場を乱したくない、傷つくくらいなら何もしない方がいい。こう考える若者に、「失敗を恐れず自分から行動しなさい」と求めても、幼少期から身についた安全行動(防衛的な行動のパターン)は、すぐに変わりません。本書では、非認知能力の育成と、その発達に深く関わるアイデンティティと所属感の支援について、幼児から大人になるまでの育ちを見通しながら解説していきます。
目次
序章 近年の大学生の姿から見えてくるもの―協働活動で浮かび上がる大学生のタイプ
第1章 大学生のタイプと非認知能力との関連
第2章 なぜ非認知能力の発達格差が生まれるのか―幼児期・学齢期の体験と非認知能力の関係―
第3章 近年の大学生の支援のあり方
第4章 職場における自律性支援
第5章 子ども時代に非認知能力を育てるには
著者等紹介
河村茂雄[カワムラシゲオ]
早稲田大学教育・総合科学学術院教授。筑波大学大学院教育研究科カウンセリング専攻修了。博士(心理学)。公立学校教諭・教育相談員を経験し、岩手大学助教授、都留文科大学大学院教授を経て現職。日本学級経営心理学会理事長、日本教育カウンセリング学会理事長、日本教育心理学会理事長、日本教育カウンセラー協会岩手県支部長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
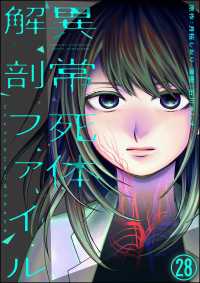
- 電子書籍
- 異常死体解剖ファイル(分冊版) 【第2…

![イコール 〈06号〉 橘川幸夫責任編集第4号 [テキスト]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/49105/491054657X.jpg)