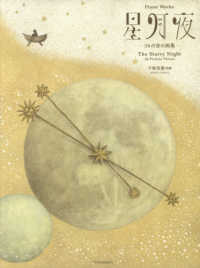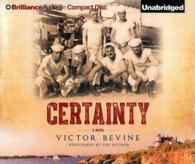内容説明
宝飾史に輝かしい足跡を残したデザイナー、かつての精彩を失ったブランド、妥協を排し挑戦を続ける新興ブランドや世界が認める不世出の天才…など、特筆すべきブランドと作家たちの活躍を独自の視点でまとめた、著者渾身のジュエリーブランド史!
目次
時代を彩ったジュエリー―流行や様式を伝えるブランドの名品
ブランドが誇る技術―一流となるための探求、開発、継承
1 老舗の宝石商―17~19世紀に花開いた伝統と革新
2 近代の名店―20世紀に誕生した宝石店
3 近年の作家―現代を牽引するジュエリー作家たち
4 ジュエリーの目利きになる―「ブランド」にとらわれず、本質を見抜く
著者等紹介
山口遼[ヤマグチリョウ]
1938年北海道生まれ。61年、同志社大学英文科卒業後、株式会社ミキモトに入社。常務取締役・営業本部長を経て、94年ミキモト役員を退任し、子会社のジェムインターナショナル社社長に就任。99年、同社を退任、リオインターナショナル社を設立し宝飾品営業に携わるとともに、流通産業へのコンサルタント、宝石小売業への教育訓練、執筆などを行う。宝石に関するマーケティング、商品開発、デザイン開発などの専門家。業務のかたわら趣味として宝飾品の歴史を研究、マーケティングも含めたジュエリーの専門家として山脇美術専門学校、山梨県立宝石美術専門学校、日本宝飾クラフト学院などにて講師を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はるき
20
クラフトマンシップに満ちた宝石たちを目で愛でる(笑)王様とか聖職者の権力の象徴だった宝石が、今は対価さえ払えば誰でも手に入る。世の中変わるものです。2020/04/17
ぱなま(さなぎ)
10
ジュエリー業界の第一人者としての著者による、ジュエリーの作製技術の高さ・難しさの解説の数々を興味深く読め、さらに色鮮やかな写真つきで各ブランドの特徴が明朗にわかるのもおもしろい。技術的な価値とは職人目線の価値判断であるが、実際に世間での知名度や人気と照らし合わせると、市場での価値の高さにも反映されている印象を受ける。ブランド品の価値が広告宣伝費と密接に関わっているのは確かだとしても、決してそれだけではないからこそ何百年もの時を経てもその輝きが人の目を誘惑し続けるのだろう。→2022/05/14
アカツキ
9
現存するしない問わずジュエリーブランド30店の歴史と名品を紹介した本。ブランドは天才がいて初めて成功できるし、いなくなった瞬間に衰退が始まる。つまり天才は座敷童。それぞれのお店の歴史をわかりやすくドラマが感じられるようにまとめてくれていて、ただこんなジュエリーを作りましたで終わっていないところが良い。著者のブランド寸評が何気に毒舌。面白かった。2022/08/07
hide
6
一世を風靡したが現存しないブランド、今もトップに君臨し続けるブランド、そして新進気鋭のブランドなど、30のジュエラーを豊富な写真とともに紹介する。/写真を眺めるだけでも時代やブランドごとの特色がなんとなく分かるし、著者のいささか重たい思いのこもった文章を読みこめばある程度の「審美眼」が磨かれるように思う。/解説の癖が強くまとめて読むと胸焼けするので、息抜き程度にちょくちょく読み進めれば自然とジュエリーに詳しくなるだろう。2022/05/27
カエル子
2
ふつうに生きていたらまったく縁のないハイジュエリーについての調査案件をうっかり引き受けてしまったので勢いで勉強中。インヴィジブル・セッティングが見事なフクシアの花のクリップはたしかに秀逸。箱根ラリック美術館へ天才作家の職人技を見に行きたくなったかも。1974年に日本で創業したギメルの「ロータス」が美しいなー、日本人女性デザイナーがヨーロッパ人を感動させるジュエリーをつくっていたとは感動ものです。著者がお孫さんに買うならギメルって言ってるし、間違いない。わたしは買わない(買えない)けども笑。2023/06/17