出版社内容情報
はにわの形やしぐさを読み解き、古墳時代の人々の暮らしを生き生きと浮かび上がらせた、画期的古代史入門書。
内容説明
前方後円墳の始まりとともに生まれ、その終焉とともに姿を消したはにわ約300年の歴史をビジュアルに追いながら、形やしぐさを読み解き、人々の暮らしを生き生きと浮かび上がらせた入門書。
目次
序章 埴輪の時代(古墳とともに300年)
第1章 埴輪ことはじめ(100年で忘れ去られた埴輪の意味;埴輪のルーツはお供え壼 ほか)
第2章 埴輪人絵巻(埴輪劇場の俳優たち;王の儀礼―まつりごとの場面 ほか)
第3章 終焉に向かう埴輪(忘れられた約束ごと;ローカルカラーあらわる ほか)
総論埴輪たちが表すものは―社会の縮図としての人物埴輪
著者等紹介
若狭徹[ワカサトオル]
1962年長野県生まれ、群馬県育ち。明治大学文学部史学地理学科考古学専攻卒業。これまでに国史跡保渡田古墳群の調査・整備、かみつけの里博物館の建設・運営を担当。かみつけの里博物館学芸員、群馬町教育委員会文化財保護係長を経て、現在、高崎市教育委員会主査。博士(史学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
NORI
24
現在、東京国立博物館で開催中の「はにわ展」の予習・復習として。日本書紀にある通り、生贄の代わりとして発生したものと思っていたけれど、あれはただの伝説に過ぎなかった!初期には円柱型のお供え用の器を並べることから始まり、そもそも人型埴輪は古墳時代も後半、5世紀末頃から作られるようになったモノだった。なにそれ、話が違うじゃん! 埴輪について、大変整理されていて、しかも平易に伝えてくれる一冊。大量の埴輪の写真。冒頭の「はにわ展」でもこの本掲載の埴輪が大量に出展されていることを確認、大変満足。2024/11/24
月をみるもの
20
「火の鳥」世代なので、ハニワは殉死をなくすために発案された、、という日本書紀の逸話を長らく信じてたんだけど、それが嘘だと言うなら実際はなんのためにこんなに大量に造られて設置されたのか?>ハニワ そもそも、日本書記が書かれたのは、ハニワ・古墳が造られなくなってからたった100年後。意図的な捏造とは考えにくいとすると、その時にはもう誰もハニワを作った理由を覚えてなかったのかもしれない。。まあ今、なんで江戸時代はチョンマゲ結ったりお歯黒してたりしたの?と聞かれても、答えられないんだから、そんなもんか。2020/04/09
ネコタ
19
序章 埴輪の時代 第一章 埴輪ことはじめ 第二章 埴輪人絵巻 第三章 終焉に向かう埴輪 総論 埴輪たちが表すものは2023/09/03
Y.yamabuki
14
豊富な写真、イラスト、表、分り易い解説。時代による埴輪とその役割の変遷がわかり面白い。こんなにも様々な埴輪が有り、しかも人物の服装や装着馬具など細かいところまで再現されているのは驚きだ。埴輪から当時の生活を想像するという視点は、目から鱗。埴輪の並びから当時の王の居館の建物群を推測したり、人物や動物から狩りの持つ意味、食料調達だけでなく、象徴性を持っていたと考えたり。眺めて、読んで、楽しい一冊。2025/07/07
しんい
11
「埴輪は語る」の若狭先生の少し前の本。埴輪の群像性、劇画性は、これまで単体でばかり理解していて興味が持てなかったのが、そういうことなのね、と群像には強く感心を持つようになった。地域的にもここまで偏りがあるとは(発掘されていないものもあるかもしれない可能性を考えつつ)。揚子江河口付近にいた「倭」族が、三国志の時代の後に、漢族の圧力で何波かで南洋や、朝鮮半島南部~九州~関西~群馬・埼玉と移民していった、という若狭説は個人的にはしっくり来たし、朝鮮半島に大和王権がなぜ進出していたのかも理解しやすい。2021/08/13
-
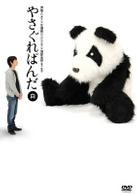
- DVD
- やさぐれぱんだ 白盤







