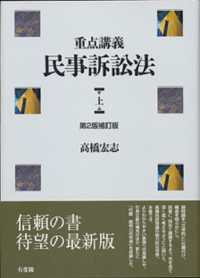出版社内容情報
いじめ、自殺、家庭内暴力、非行……子どもたちを破滅へと追い込んでいく元凶はなにか。人間を「モノ」へと仕立て上げていく「工場化した学校」と、それを求める労働の現場をルポルタージュする。タイトルは、女の子の人格の崩れ、生への欲求の衰えを書いた一文から。 ■■■山田太一氏(シナリオ作家)=ドキドキしながら読んでいます。あの時代がなまなましく蘇って、とにかく面白いです。■■■黒田清氏(ジャーナリスト)=この本を手にした夜は朝がた近くまで眠れなかった。若い夢追い人よ、この本を読んでジャーナリズムの門を叩いてくれ。■■■樋口恵子氏(評論家)=当代一流のジャーナリスト斎藤さんが、時代の水先案内人として警鐘を鳴らしつづけた作品を通読すると、さながら被治者の側から見た戦後通史の観がある。■■■松本清張氏(作家)=その寝食を忘れた熱意と、精力的な追及心と、工匠を思わせるような取材技術とは、最近とかくマンネリ化したといわれる新聞・雑誌記者を奮起させるであろう。■■■ ★★★朝日新聞評=ジャーナリストとして生きた著者の深いエートスが、詩的に、しかし剛直に表現されていて、心を打たれる。★★★三田評論(内海愛子氏)評(1991年1月号)=克明に取られた取材ノート、短い記事の裏につぎ込まれた情熱、社会的弱者への温かい眼差し、権力犯罪への怒り--時に応じて見せるジャーナリストのこころの動きが読みやすい文章の中から浮かび上がり、多くの時間を経過した今も読む者の心を打つ。すぐれたジャーナリストが、たぎるおもいで書き綴ったこれらの書を読み終えて、深いため息とともに自分の過去を振り返る人も多いだろう。★★★ ●●●本書「まえがき」より抜粋=子どもたちは救われないなあ……と考え込まされる場面に、近ごろよくぶつかる。先夜、民放テレビで放映していた市立中学受験戦線の舞台裏もそのひとつだった。“公立中学ばなれ”は年々いちだんと進んで、東京・山手の小学校などには6年生の7、8割が私立中学を受験するところが少なくないようだ。近ごろは早くも小学校2年生から進学塾へかよって受験勉強に明け暮れる子どもが多くなっているという。そんな勝ち抜きレースの過熱状態につけ込む受験産業屋も当然出てくるわけだが、そのテレビ番組に登場した塾の場合は、一カ月の特訓で必ず希望の私立名門校に合格させるという約束で、300万円の特訓料を取っていた。いったいどんな特殊技術があるのか、それほどの大金を要求する業者のしたたかさにもあきれるが、買えるものなら受験用学力を現ナマで買ってしまおうという親も親だ。ところが、この番組を見た親たちから、その特訓塾の連絡先を教えてほしいという電話がテレビ局に相次ぎ、中には「うちは1000万円出してでも合格させてやりたいから、ぜひ教えて」とねばる母親もいたそうである。欲しいものはなんでもカネで買うのだ、自分にはそのカネがある、なにが悪いのかという傍若無人の暴力的エゴイズムを感じさせるところは、いま世界のあちこちで怨嗟と顰蹙のタネをまき散らしている“カネ持ち日本”の姿そっくりだ。札束と引き換えにどんな“学力”が子どもの身につくのか。親の欲と見栄を背に、栄光レースを勝ち進んでいったあげくに、どんな「人間」ができ上がるのか。寒々しい想像が広がる昨今の教育状況だが、これは1960年代に、日本が経済成長の急坂を昇りはじめたころ、「教育」が「経済」の下僕に位置づけられ、カネもうけの手段にさせられたときに胚胎していた矛盾の、必然的な結果である。そしてそれは、高度成長路線の最前線にあった労働現場に、経済効率最優先の大合理化の波が襲い、「人間」をカネもうけの道具にしていった足どりとぴったり重なり合う。この「取材ノート」第三巻には、高度成長を軸に、「労働」と「教育」の現場を、あちこち取材して歩いていたころの記録を収めることにした。●●● 【主要目次】▲▲第1章・合理化列島をゆく=突き上げる空に---高度成長時代の労働者たち(入院生活/工場から工場へ/石鹸の匂い/割を食う人々)/農村工場に陽は落ちて---コンベヤー無惨(夜の列車/谷間の町/主婦たちのあす/工場閉鎖/厳しい冬へ/風圧の発生源)/わしがやらねばだれがやる!---総力献身求める管理ファシズム(黙っている人々/競輪・競馬・酒・女/Xさんの嘆き/コストダウンの旋風/あなたが主役)/繁栄日本のカラクリ装置---労働現場でみえてきたこと(高度成長時代とは/生産現場でなにがはじまったか/労働の非人間化強まる/職場の楽しみが消えた/欲望地獄へ落とす/蒸発する妻たち/総ぐるみ動員体制/運命共同体への変質/青年労働者の状態/コンベヤーの娘たち/君が舞う花まつり/弱者への想像力を) ▲▲第2章・日本教育工場=子どもたちを破滅させる元凶はなにか(太陽で自殺したい/栄光レースの果てに/「人づくり」の正体/経済の従属物に/中心原理はなにか/教育的言辞に彩色されて/生活の根っこから)/合理化帝国の教師たちは(企業の論理を学校へ/松下幸之助に学べ/分秒きざみの学校/小官僚の群れ/研究発表の裏で/働く者同士なのに/ひとつの決算)/学校の顔と工場の顔/親のうしろに寝そべるのはだれ?/教え方教えます---「法則化」教師たちはどこへ行くのか(ほんものかニセモノか/よい子ちゃんのお教室/一刀両断の裁定/ゴミを拾わせる方法/危ない思考回路/生産性向上の管理手法/学校でのQCサークル/理念なしの危うさ)/自分は自分の主人公/子どもの内面へ熱い視線を(大自然を武器に/切実な必要に迫られて/人生は闘いとるものだ/師と人生を語り合う/生活の土台の事実を/徹底的に子どもにつく) ▲▲第3章・そして世紀末へ=子どもたちの涙/非行なき非行/異端をおそれる子どもたち/娘たちは根腐れていくのか/人間の自立のためにいまこそ/遺産
内容説明
ジャーナリスト斎藤茂男が、人間貧因化がすすむ繁栄日本のカラクリ装置をあばく。取材記者のノート。
目次
合理化列島をゆく(突き上げる空に―高度成長時代の労働者たち;農村工場に陽は落ちて―コンベヤー無惨;わしがやらねばだれがやる!;繁栄日本のカラクリ装置―労働現場でみえてきたこと)
日本教育工場(子どもたちを破滅させる元凶はなにか;合理化帝国の教師たちは…;学校の顔と工場の顔;親のうしろに寝そべるのはだれ?;教え方教えます―「法則化」教師たちはどこへ行くのか;自分は自分の主人公;子どもの内面へ熱い視線を)
そして世紀末へ(子どもたちの涙;非行なき非行;異端をおそれる子どもたち;娘たちは根腐れていくのか;人間の自立のためにいまこそ)