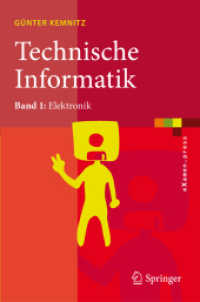出版社内容情報
「私だったらここに入所したい」
「ここには入りたくない」
日本全国の特養ホームを、実際に見て歩き、入所者の住み心地でチェックする。
巻末には、福祉関連の行政通達やサービス内容、費用負担などについての資料を収録した。
【書評再録】
●読売新聞評(1997年8月15日)=北は函館から南は那覇まで、計18ヵ所の特別養護老人ホームを歩き、入所者の「住み心地」をチェックした労作。「私が入りたい特養の条件は、町中にあり個室があって1人の行動が保障されること」という著者の願いに共感する人も多いのではないか。
●北海道新聞評(1997年7月29日)=老人介護はこれからが正念場だと関係者に迫る書。
●日経ビジネス評(1997年7月21日)=市民としての視点で、素朴な疑問、感想、要望を書き綴ることで、温かみのあるルポルタージュに仕上がっている。巻末には、福祉関連の行政通達や、サービス内容についてのアンケート結果などが収録されており、特養関連の資料としても貴重である。
【読者の声】
■男性(35歳)=とても楽しく、また考えさせられながら、一気に読んでしまいました。特養を「人間が住める場所にしたい」と思って、いろいろ努力していますが、いたらないことばかり……。自分の力の無さに落ち込んでばかりです。この本で得た、アイデアや考え方を今後の施設運営に生かしていきます。
【内容紹介】本書「はじめに」より
老人ホームを訪ねる旅をしてきた。高齢化社会というと、反射的に「介護」「ぼけ」であるとか「老人ホーム」という言葉が浮かぶが、実際は、元気で過ごしているお年寄りのほうがはるかに多い。そんな元気な老人のルポを書くほうが喜ばれるのではないだろうか。
それなのになぜ「暗い」と敬遠されがちな老人ホームのことを書くのか。そこに老人ホームがあったから、という実に単純な理由が発端だった。三級ホームヘルパーの養成講座の実習で、生まれて初めて特養ホームに行った。それがきっかけで、夜勤専門寮母になった。そして、老人ホームで生活している「物言わぬ」人たちと会って、口先女と家ではいわれている「物を言う」戦後世代の私はびっくりした。どうしてお年寄りはそんなに遠慮したような笑顔をするのか。なぜ、そんなに小さくなっているのか。なぜもっと文句を言わないのか。そこでの一年半の経験から前著「特別養護老人ホームの夜」を書き、ますます特養は気になる存在になった。
前作は自分の老後のためにお年寄りを利用したという批判があった。それは当たっていると思う。私が生まれた1946年ごろは、平均寿命は女が53、男は50歳くらいだったのが、90年にはそれぞれ82歳と76歳を超えた。いまのお年寄りは、日本が超高齢社会に向けて進んでいくその最前線におられ、すべて初めての経験をされている。そんななか、多くは先に例を挙げた方たちのように自分の行く手を切り開きたくましく暮らしておられ、その知恵を私たちにも分け与えてくれている。その一方で、こんなに長生きできるとは思わず、なんら心の準備もできないまま、不本意な生活を余儀なくされている方もおられよう。そのどちらも私たちにとっては貴重な「お手本」である。まさに温故知新であると私は思う。そういう意味で、私はお年寄りを利用しているが、第一走者のバトンをしっかり受け取って、また次の世代に受け継ぐことが、われわれ団塊の世代の役割ではないだろうか。ヌーの大群のように、草の1本も残さず食べ尽くし、荒らし尽くしてはこの世を去りたくない。
地元をはじめいくつかの特養ホームを訪れたあと、96年からは腰を据えて日本の特養ホームめぐりを始めた。自分の勘を頼りに「全国老人福祉施設要覧」という名簿を繰って、なんら予備知識もないひらめきで訪れるべき施設を選んだ。全国の特養の数は名簿によれば2770、そのうちの30ヶ所くらいを巡る計画だ。途中で計画を変更したが、終ってみると、平均的な日本の特養ホームと思われるところから、ここはちょっとという施設、いいんじゃないという施設などうまい具合にバラエティーに富んだ選択になっていた。判断の基準は「自分が入りたいと思えるホーム」。果たしてそういうホームと出会えたのか。
なお本文は読みやすさを中心に考え、根拠となる資料の掲載や言葉の説明は省いた。巻末に資料編を設けたので、興味のある方はそちらも併せてお読みいただければと思う。
【主要目次】
▲▲第1章 私が特養ホームめぐりを始めたわけ
▲▲第2章 半歌仙 日本特養めぐりの巻
▲発句 初場所や星取表を張りて待つ……国立市・くにたち苑
▲脇 関脇となる長寿番付……八王子市・みやま大樹の苑
▲第三 新年の国際電話に耳かたむけて……新宿区・原町ホーム
▲表四 韓の国にもナザレ園とか……茨城県・ナザレ園
▲表五 寝静まる杏の里はおぼろ月……上田市・別所温泉長寿園
▲表六 夜勤ナースの足音を聞く……板橋区・東京都板橋ナーシングホーム
▲裏一 ひな祭り男は陰で将棋指す……大阪市・あっとほうむ
▲裏二 みなで歌いし鐘の鳴る丘……群馬県・鐘の鳴る丘愛誠
▲裏三 一缶のビール二人で分かち合う……奈良市・万葉苑
▲裏四 好物詰めて今日も面会……神戸市・協同の苑 六甲アイランド
▲裏五 この季節しゃこがうまいと運転手……尾道市・浦崎寮
▲裏六 観音様のお顔に見入る……長野市・大本願ユートピアわかほ
▲裏七 慰霊碑にかかる三日月明けやすし……那覇市・首里厚生園
▲裏八 おんなですもの浜遊びせん……石川市・楽寿園
▲裏九 飛行機の爆音避けて二重窓……宜野湾市・愛誠園
▲裏十 ナイトシアター子連れ狼……土岐市・美濃陶生苑
▲裏十一 雪とけて花の便りも聞こえくる……秋田市・大平荘
▲揚げ句 かざぐるま舞う別荘の岡……函館市・旭ケ岡の家
▲▲第3章 私の入りたい特養ホーム
内容説明
人生の最終コーナーを曲がるとき、自分なら、どのような場所を選ぶだろう―団塊時代のルポライターが、北海道から沖縄まで、全国の特養ホームを回って考える「終の住処」考。これまで運営者の側から考えられがちだった特養ホームのあり方を、私だったらここに入所したい、ここには入りたくない、と入所者の住みごこちで判断する画期的ルポ。
目次
1章 私が特養ホームめぐりを始めたわけ
2章 半歌仙―日本特養めぐりの巻(国立市・くにたち苑;八王子市・みやま大樹の苑;新宿区・原町ホーム;茨城県・ナザレ園;上田市・別所温泉長寿園;板橋区・東京都板橋ナーシングホーム;大阪市・あっとほうむ ほか)
3章 私の入りたい特養ホーム
-
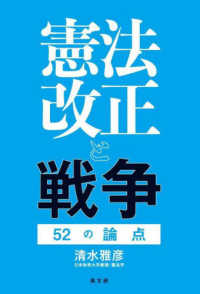
- 和書
- 憲法改正と戦争52の論点