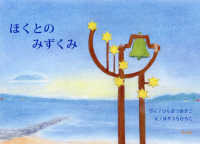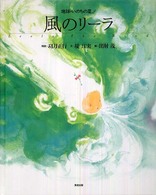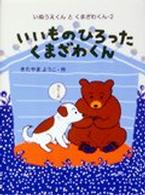出版社内容情報
長良川の生物相調査に長年関わってきた著者が、運用から20年近くたつ長良川河口堰の生物相への影響を検証する。
長良川の生物相調査に長年関わってきた著者が、河口から40キロにも及んだ感潮域の生物相調査や地域住民による環境モニタリングの意義など、運用から20年近くたつ長良川河口堰の生物相への影響を検証する。
プロローグ
川下から上流へ押し流される?
九死に一生を得た足立さん
第一章 河口堰建設前夜
長良川下流域生物相調査団結成
無数のベンケイガニ
ベンケイガニの棲息密度調査
建設省中部建設局・水資源開発公団中部支社よりの公式回答
建設省・中部建設局訪問
不信感を抱かせる5か月後の回答
不誠実な建設省からの回答 その1
全くの欺瞞・利根川河口堰上流のクロベンケイガニ
ベンケイガニの生活史
カニの雌雄
絶滅は必至、堰上流のベンケイガニ
32キロ地点まで生息する多毛類(ゴカイの仲間)-頭(顔)で個体数確認 ゴカ
イ・イトメ
イトメの生殖群泳
イトメの自切
大活躍の魚類班
哺乳動物班 決着確認できず・関ヶ原の合戦-コウベモグラ対アズマモグラ
新種・ヤドリウメマツアリ発見-昆虫班
絶滅危急種・チュウヒ等120種確認
野鳥班の活躍
植物でも絶滅危急種・ミズアオイ、タコノアシを確認-植物班
不誠実な建設省からの回答 その2-「河口堰を建設しても3分の1強も残る汽水域」
生物学的汽水域・32キロ地点まで
次々変わる河口堰建設目的-最初の目的は利水
利水から治水、そして塩害防止へと変わる建設目的
長良川下流域生物相調査団の実態
『長良川下流域生物調査 中間報告書』発表-1991年12月
「長良川河口堰建設差し止め訴訟」への証人出廷-調査団団長・山内克典先生
6月16日の裁判記録から
9月1日の裁判記録から
調査項目の追加
潮時表の携帯
塩分濃度の調査
魚群探知機による塩水楔の視覚による確認
マウンドを乗り越える塩水楔
採取・測定したマウンド上流の塩分(塩化物イオン)濃度
調査での逸話
川面に潮汐の影響が及ぶ感潮域の上限は40キロ地点
水準測量による堪水域上限の調査
天然アユの仔魚は無事海に到達できるのでしょうか-長い堪水域、そして堰を越
えての海域への落下
海産アユと湖産アユ
20キロ地点で海洋性のプランクトンも採集 日本で2例目、珍しい汽水性ソコミ
ジンコ棲息確認-プランクトン調査班
不誠実な建設省からの回答 その3
「ユスリカの大発生はありません」「ユスリカは喘息の原因ではありません」
嘘で塗り固められた魚道実験
不誠実な建設省からの回答 その4-「アシ原は再生します」の詭弁と無益な行為
「この紋所が目に入らぬか!」-時代劇・水戸黄門を思い出す建設省(現・国土
交通省)訪問
『長良川下流域生物調査報告書』刊行-1994年7月
第二章 河口堰竣工後
試験堪水と「長良川モニタリング委員会」の設置
写真の無断使用問題
「円卓会議」の開催
環境問題・あげあし取りに終始した1回目-3月27日
円卓会議の継続-続会・4月15日
汽水域の消失を全面的に認める建設省
ビデオ放映-ベンケイガニの繁殖、イトメの生殖遊泳
地盤沈下による、汽水域、海域ともに上流側へ
堰下流域の水質は層状構造になり、対流が生じる
DO対策船問答-莫大な税金の無駄遣い
爆笑とヤジで会場騒然
植物性プランクトン(藻類)大発生の懸念
ユスリカと喘息問題での粕谷発言
魚道の効果は100パーセント・漁業補償は130億円
アユの「釣り堀化」・海産アユの種苗放流
「長良川下流域生物相調査団」の存続と調査活動続行
第三章 河口堰稼働後の長良川
「長良川研究フォーラム」の開催
フォーラム 4回で打ち止め
河口堰稼働後の調査団
河口堰による流下仔魚(アユ)への影響
仔アユの流下速度低下確認
流下仔アユの死亡激増
小型化する長良川のアユ
堰上流では魚類多様性の激減
予測外れ、ユスリカの大発生は空振り-ユスリカも棲めない川底
マシジミも予想外の激減
オオシロカゲロウの集団発生
止水性ユスリカとオオシロカゲロウの生育場所
堰直上流域は環境ホルモンの蓄積場所
深刻な河口堰下流域-酸素不足の川底とヘドロ・有害物質の集積場
足立孝さん手作りのコアサンプラー
粕谷概念図を10年後に証明
合流後も揖斐、長良両河川の底質差違甚大
アシ原の衰退・消滅
調査団の解散-長良川下流域生物相調査報告書2010河口堰運用一5年後の長良川』刊行
エピローグ
漁師さんから聞いたこと
河口堰の目的は?
本物の民主主義を
ありがとうございました
【著者紹介】
1939年大阪生まれ。岐阜大学生物学科卒業後、岐阜東高等学校赴任。2000年退職。「長良川下流域生物相調査団」発足から解散までの20年間事務局長として、長良川の変貌を見守り続けた。著書には、『カモシカ騒動記』『ぼくはニホンカモシカ』、30数回に及ぶアフリカへの調査旅行をもとに執筆した『ぼくゴリラ』(以上築地書館)のほか、自身のルーツを探った『豊臣方落人の隠れ里』などがある。また、共著として、『長良川下流域生物相調査報告書』、『長良川下流域生物相調査報告書2010------河口堰運用15年後の長良川』(以上長良川下流域生物相調査団)、『長良川河口堰が自然環境に与えた影響』(日本自然保護協会)などがある。
内容説明
長良川の生物相調査に長年関わってきた著者が、河口から40キロにも及んだ感潮域の生物相調査や地域住民による環境モニタリングの意義など、運用から20年近くたつ長良川河口堰の生物相への影響を検証する。
目次
第1章 河口堰建設前夜(長良川下流域生物相調査団結成;無数のベンケイガニ;ベンケイガニの棲息密度調査 ほか)
第2章 河口堰竣工後(試験堪水と「長良川モニタリング委員会」の設置;写真の無断使用問題;「円卓会議」の開催 ほか)
第3章 河口堰稼働後の長良川(「長良川研究フォーラム」の開催;フォーラム四回で打ち止め;河口堰稼働後の調査団 ほか)
著者等紹介
伊東祐朔[イトウユウサク]
1939年大阪生まれ。岐阜大学生物学科卒業後、岐阜東高等学校赴任。2000年退職。「長良川下流域生物相調査団」発足から解散までの20年間事務局長として、長良川の変貌を見守り続けた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
尾張こまき